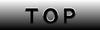― 22.夕陽〜Abendsonne〜 ―
人によって感性は違う。同じものを見たとしても、それに対する感想は正しく十人十色である。しかも、その日の機微によってそれは如何様にでも移り変わる。まるで、全く別のものを見ているかのような反応をする。例えばそう、全ての者に等しく訪れる、夕刻の斜陽のように――。
何かの出来事においても、それは当て嵌まるだろう。一方にとっては良い想い出であるとしても、他方からしてみればそうではないかもしれない。それを美しいと思う者も居れば、疎ましく思う者も居る。正邪で測れるものではない。ただ、その者達の感性によるのだ。
或いはそれが、時に人を惑わせるのかもしれないが――。
窓の外には穏やかな陽光の下を行き交う人々が見える。しかしその光景は、自分の見慣れたものとは少し違う。今日は休日ではなくて平日である事を意識しているからなのであろうが、人々の動きは何処か忙しないように思えてならない。
不意に取れた有給を持て余して、敏行は自宅のベランダの窓から表を眺めていた。確かに元々この日に有給を取りたいと申請はしていたが、その日は人が居ないからどうしても出てくれと頼まれ、休むのを諦めていた。ところが前日の晩になって、当初出られない予定だった筈の同僚が出られる事になり、急遽有給が認められてしまったのだった。とはいえ、休めないと思って予定も全てキャンセルした後に休みが舞い込んで来ても、正直やる事がない。平日の昼間では、敏行の交友範囲の中でも殆どの人間が仕事をしている時間なので、誘える相手も居ない。
そんな感じで午前中を無為に過ごしてしまった後、敏行は取り敢えず出掛ける事にした。このまま時間を無駄にしても勿体無いし、外に出れば家で引き篭もっているよりは有用な時間の使い方が出来るだろう。そう思って、敏行はインプレッサワゴンに乗り込み、白昼の街へと出向いて行った。
しかし、昼食を取るのも一人ではそれほどの時間を要さないし、買い物もウインドウショッピングだけで何時間も掛けられてしまうようなタイプではない。やがて目指す当てがなくなった敏行だったが、不意に一つの目的地を思い立つ。
「そうだ。水看さんの所へ行ってみよう。今回の仕様の感想も言っといた方が良いだろうしね。」
この時間はガレージ木之下も通常業務を行っているので、水看も敏行と話をしている暇はないかもしれないが、他にも話せる工員は居るし、それに誰も手が空いてなかったとしても、ガレージ木之下なら時間を潰し易い。何よりも行く当てが出来た事を歓びつつ、敏行はガレージ木之下へと車を向かわせた。
しかし、間の悪さというのは続くものである。
「うわ……定休日なのか……。」
ガレージ木之下の敷地はそれなりの広さがあるので、近くに来た時点でも静けさは感じていたが、人気の全くない店の玄関口に掛かる「定休日」の札を前にして、敏行はいよいよその事実を受け入れざるを得なくなる。それでも水看だけは居ないかと様子を窺ったが、それも無駄に終わる。
「何だよ……。どうして今日に限って……。」
考えてみれば確かに今日は定休日だと知っていたのだが、此処を訪れようと思い立った時には全く忘れていたし、結果として期待を裏切られた形になるので、敏行にとってみれば勝手な話とはいえ糠喜びをさせられたようなものだった。
「さて、どうしたものかな……。」
無人の工場の敷地の前で一人敏行は考え込んでいたが、やがて携帯を取り出してメールを打ち始める。
「後は美由だな……。仕事かなぁ……。」
美由はコンビニエンスストアで働いているので、基本的に暦とは無関係であり、シフトの入れ替わりもそれほど珍しくないので、いつが休みなのかはその時にならないと分からない場合も多い。今日は悉く予定を外されているので、もはや駄目元といった想いでメールを送ってみた敏行だったが、返信はすぐに帰って来た。
「お、ようやく。」
それを見て、敏行は嬉しそうな顔をする。今日は早朝から昼までのシフトだったので、既に帰宅して洗車しているとの事だった。洗車なら自分も手伝えるし、居ても邪魔になる事はないだろう。今度こそ都合の合う人間が見付かったと思いながら、敏行はガレージ木之下を後にした。
暫くは晴天続きの予報であるし、今日の天気も雲一つない快晴であったので、正しく洗車日和である。明るめのピンクのボディカラーは比較的汚れが目立たないが、暫く洗っていなかったので気になり始めて来ていたところだった。布製の幌を持つロードスターを洗車機に入れるのは流石に気が引けるし、既に別の車への乗換えを検討しているとはいえ、まだ暫くは共に走る事になるであろうこのロードスターにも愛着はある。たまにはこうして手洗いしてやるのも、気分が良い。
とはいえ、作業は結構時間が掛かるものだ。それに洗車そのものがそれ程好きというわけではないので、一人で黙々とやっていると少し寂しさを感じる事もある。その為に、敏行が来てくれれば、作業も早く終わらせられるし、話し相手も出来て一石二鳥である。――もう少し前であれば、素直にそう考える事が出来たであろう。
先日、喫茶店では自分でも気付かぬ内に悪態を吐いていた。大した事でもないのに、敏行に突っ掛からずには居られなかった。慌てふためく尊を見、やって来た楓に宥められ、ようやく自分のした事に気付いた。逆に言えば、それまで自分の悪態に気付けなかったという事でもある。
「……ホントに、私は何を焦ってるんだろう……。」
あの後、楓が敏行達にしたらしい話を、美由も聞かされていた。楓は美由達がしている“走り屋”という行為に、かなり理解を示してくれてはいるが、本人は特に車が好きというわけでもなく、当事者にはなり得ない。ただ、それだけに客観視する事が出来るのだろうし、何よりも楓は変なところで鋭い。その娘である美由は、楓の言葉を無下にしてはいけないという事はよく分かっていた。
敏行に対して複雑な感情を抱くようになったのは、今に始まった事ではない。あの日、敏行と再会を果たした時から、ずっとだ。敏行が走りを知る事により、何かを失って辛い経験をさせたくないという想いと、走りの世界であれば敏行の側に居られるのだという想い。その板挟みに、美由は苦しみ続けて来た。
しかし、それを加味したとしても、この間の敏行への反発は少々度が過ぎたかもしれない。それが楓の言う焦りから来るものなのか――。今の美由には、全く持って分からなかった。
ともかく、敏行への感情が以前にも増して複雑になって来ているのは間違いない。それ故に、敏行と顔を合わせる事に気まずさを感じてしまう部分もあった。恐らく、敏行を含め他の人間は、自分が思っているほどに敏行に対する態度の事を気にしてはいないのだろうが、自分の中ではどうしても気持ちの整理が付かない。
嘘を吐いてまで、敏行を追い返す理由はない。けれども、明るい表情で敏行を迎えられる自信もない。メールでは仕事が明けて洗車をしている事だけ伝えたが、それは来て良いという意思表示と取るのが普通だろう。
敏行は来る――。その事で気を病んでいる自分が情けない。嘗て喫茶店での同僚だった時は、気兼ねなど微塵も感じず敏行に近付く事が出来たのに――。時間とは、こうも残酷なものなのか――。
やがて、敏行はやって来る。グレーのインプレッサワゴンに乗って。そういえば、昼間に敏行と会うのは久し振りのような気がする。やはり、敏行との絆は深夜の走りに大きく依存しているのだなと再確認する暇もなく、車から降り立った敏行が声を掛けて来る。
「お、やってるね。」
爽やかな青年と称するのも何だが、敏行の様子に邪気など感じられる筈もない。元よりそれだけに、深夜の幕張で会う時とはやや表情が異なるようには思える。どちらかといえば、喫茶店でバイトをしていた時の雰囲気に近いのかもしれない。雑念があるのは、自分か敏行か、はたまた双方なのか――。過ぎる想いを押さえ付け、美由も元気良く言葉を返す。
「うん! 時間があって、尚且つ良い天気が続く時って、なかなかないからね。で、来たからには、当然手伝ってくれるんだよね?」
上辺を取り繕う事には慣れている。ただ、明るさも半分は本心なのだとは信じたかった。
「ああ。そのつもりだよ。今日はもう完全に時間を持て余しちゃってるからね。」
早速に腕捲りをしてやる気を見せる敏行を見て、美由は思わず吹き出した。そして、そこで反射的に笑えた自分に安堵した。
ロードスターは元々小型である上に、ルーフ部分を除外してしまえば、他の車と比べて洗う面積はかなり少ない。しかも二人掛かりであるので、洗車は手際良く進んで行った。
「こうして美由の車のボディを見るのは初めてだけど、細かい傷も少なくて、ホントに綺麗だよね。新車で買ったんだっけ? このロードスター。」
ワックスを拭き取りながら、敏行が感心したように訊いて来た。
「新古車だから、まぁ、似たようなものかな。たまたま良いのを見付けられたからね。それに、私の初めてのマイカーだからね。そりゃ、愛着も湧くってもんだよ。」
「それは分かるなぁ。僕も免許取る前からインプレッサが好きだったけど、大学生の頃は流石にインプは乗れなくて、32のGTS4に乗ってたからね。4駆だから良いかと思ったけど、重いわパワーないわで散々だったなぁ。でも、色々遊んでみて扱い方も覚えたりして、今となっては良い思い出だよ。」
GTS4は目標の車を手に入れるまでの足掛かりとして買ったに過ぎなかったのだが、やはり初の自分の車という事で、当初自分が考えていたよりも思い入れた。一方の美由は、今もこのロードスターに乗り続けており、しかも性能も申し分ない。敏行よりも更に深く心を掛けているとしても、不思議はない。
「それでも……車は愛着で大して速くなるわけでもないしね。美由のイメージにはロードスターが合ってる気もするんだけど、今以上のレベルを求めるとなれば、流石にベースがコンパクトスポーツでは限界があるだろうから、乗り換えたくなるのもしょうがないと思うよ。」
その言葉を述べている内に、敏行の目が僅かに据わった気がした。本人は気付いていないのだろうが、逆に美由は敏感だ。敏行が走りの話をする時の目――それは美由の余り好まない敏行の姿だった。
「うーん、私がロードスターに乗ってるところしか見てないからなんじゃないの? きっと別の車に乗ってれば、その車のイメージになったんじゃないかなぁ。」
とはいえ、あからさまな拒否反応を示すわけにもいかないし、何より自分が勝手な感情を抱いているだけであって、走り屋と称される人種ならばこうなるのも珍しい事ではなかろう。美由は当り障りのない返答をする。
「それもあるんだけどさ。やっぱり僕にとっては印象が強烈過ぎたんだよね。もう、1年以上前になるのか……。美由と再会した日に見た、あのロードスターの走りはさ……。」
敏行が遠い目をする。1年前の再会の日――。それは美由の側にとっても、重要な意味を持つ。だがそれだけに、その日の事に触れられると、何と言葉を返せば良いか分からなくなる。ややあって、美由はゆっくりと口を開く。
「……そういえば、敏ちゃんはどうしてあの日、私に会いに来ようと思ったの? いや、会いに来てくれた事は嬉しかったんだよ? でも、急な事だったから、どうしたのかなって思ってた部分もあったんだよね……。」
すると今度は敏行が言葉を詰まらせる。今更な話ではあるが、美由の言う事も尤もだ。それまでもメールのやり取りなどで連絡を取ってはいたが、顔を合わせた事はなかった。事実、敏行は美由と実際に会おうと言う事にやや抵抗を感じたほどだった。――それでも美由に会いたいと思った理由。洗い浚いという程までには行かないが、ある程度の理由を話すには良い機会かもしれない。
「まぁ、僕も色々あってね……。一応、就活は順調に行って、志望した所に入れたんだよ。給料も悪くないし、時間も比較的きっちりしてるし……。だけどね……。どうしても満たされていないように思えて、仕方なかったんだ。職場の同僚とも、仲は全然悪くはないんだけど、深入りは出来ないっていう感じだったし、仕事も漫然とこなしているだけだったしね。……そんな中でも、走りに行くのだけは楽しみだった。収入が安定したお陰で、念願のWRXも買えたし、それはもう毎晩のように走り回ったもんだよ。……僕の勤めている会社は、結構大きい所でさ。確かに自分も会社の歯車に組み込まれているとはいえ、僕一人が欠落したところで、会社が大きく傾く事はない。僕個人の働きなんて、然したるものじゃないんだと考えると、何だかやる気が殺がれちゃってね……。生活の為だと割り切るようにはしてたけど、どうにも寂しく感じてしまう事も多かったかな。」
そんな風に思う自分は、考え過ぎなのだろうとは感じていた。同僚と深い付き合いはなかったから、プライベートで仕事の事をどう思っているかは知る由もないが、少なくとも傍から見る分には、自分のような悩みを抱えているとは到底思えなかった。またそれが、同僚と一定の距離を置いてしまう理由の一つでもあったのかもしれない。
「だから、走ってる時は楽しかった。全てが個に委ねられる、この世界が……。車を用意するのも、この場所へ来るのも、そして走るのも、全ては自分次第。自分から踏み出さなければ、何も始まりはしないこの環境が、会社員としての僕とは正反対でに思えて、楽しかったんだ。ある意味では、此処でこそ生を実感出来た。そんな風にも言えるのかもしれないね。」
初めはそれで相殺出来ていた。いや、夜の走りの方が勝っていたくらいであったので、昼間の仕事も必要以上に辛くは感じなかった。
しかしながら、それも長続きはしない。両者の力関係は次第に拮抗して行き、そして逆転する。仕事での鬱積が、走っても走っても晴らし切れなくなってしまった。夜が明けてしまえば、どうせまた現実へと引き戻される――。やがて敏行は、走る意義すら見失いそうになるのだった。
「……走るのが大好きなのは間違いない筈なのにね。だから、それすらも楽しめなくなってしまうのが怖かった。そうなってしまったら、僕は終わりなんじゃないか……。大袈裟かもしれないけど、当時の僕は本気でそんな風に考えてたね。」
敏行の表情にやや影が差す。昔の話とはいえ、深刻な事態だったのだろうという事は、その様子を見る美由にも容易に察せられた。
「そんな時だったかな……。ふと、美由の事を思い出したんだよね。」
それから敏行はまた顔色を変えた。そして、此処から先は、語弊を覚悟で聞いて欲しいと念を押した後に、遠い目をしつつ、ゆっくりと言葉を続けた。
「……喫茶店で僕が働いてた頃の美由は、心底無邪気で楽しそうだった。車の話をしている時の美由の瞳は、本当に輝いていた。そんな美由の姿が脳裏に浮かんで……そして、会ってみたいと思ったんだ。僕が失ってしまったもの……何よりも尊んでいた走りを楽しめなくなった理由……。美由に会えば、それが何なのか分かる気がしたんだよ……。」
実際に会い、そして深夜の幕張を走った瞬間に、敏行が期待した嘗ての美由の姿はもうないのだと悟った。それでも、当時の敏行が彼の言葉通りの事を期待していたのは事実であるし、もしかすると――未だにそんな美由の姿を引き摺っているのかもしれない。
「ふーん。そうなんだ……。」
しかし、美由の返事は素っ気無かった。もう少し神妙に受け止めてくれると思っていた敏行は、少々肩を落とした。
だが、それを見た美由は、しまったと思った。うっかり気のない台詞を吐いてはしまったが、敏行の言葉には多くの感慨を抱かずにはいられなかった。寧ろ、そうだからこそ、言うべき言葉が見付からず、咄嗟に無感情な反応をしてしまったのだった。
「まぁ……確かに私も、あの頃の方が……素直に車の事を楽しめてたと思う時はあるよ……。」
敏行の言葉を積極的に受け止めるべきか、消極的に突き返すべきか、交錯する複雑な想いから答えを見出す事など出来る筈もなく、美由は目線を合わせる事もせず、元気のない様で言葉を紡いだ。ともすれば震えてしまいそうになる声を押さえながら。しかし、それ以上言うべき言葉が出て来ず、重い空気を漂わせながら美由は手だけを動かしていた。
「ごめん、敏ちゃん。そこのスポンジ取ってくんない?」
それでも、この沈黙を無理にでも打破したくて、美由は敏行への頼み事を口実に言葉を発した。敏行も一瞬戸惑いはしたが、美由の意図を察したのか、落ち込む気持ちを表に出す事無く、美由にスポンジを渡した。そして、暫くはまた押し黙っていたが、やがて敏行がゆっくりと口を開いた。
「なぁ……。美由は、どうなんだ……?」
それが何を訊く問い掛けなのか、美由にはすぐに理解出来た。そもそも、自分から切り出した話なのだ。どうして、私に会いに来ようと思ったのか、と。そして、敏行の側ばかりに告白をさせておいて、自分の方はだんまりを決め込むのは、余りに身勝手な話だ。だが――身勝手と分かっていても、その問いに直接的に答える事は出来ない。美由の側には、それほどまでの理由があった。
だからその代わりに、はぐらかす意味も込めて、こう言った。
「……敏ちゃんとはこうしてる時の方が、走ってる時よりも楽しいかもしれないね……。」
浮かべる笑みは、苦々しさを感じさせる。敏行の質問に対する回答とは到底いえない言葉。しかしそれは、美由の想いを具現していた。
帰途に着くインプレッサの中、敏行の様子は決して浮いてはいなかった。美由の拒否感すら滲ませる反応への落ち込みと共に、美由の美由の最後の言葉が余りにも不可解であったが故に、怪訝な表情を未だ浮かべたまま、車を走らせていた。
「走っている時よりも楽しい……って? 一体、どういう意味だっていうんだよ……?」
それより後、二人は会話と呼べるような会話はしなかった。必要最低限の言葉を事務的に交わし、挨拶だけをしてその場を去る。その言葉を聞いた敏行には、そうするのが精一杯だった。
街の喧騒はするものの、敏行が帰って一人取り残された美由は、やけに静かになってしまったように感じていた。そもそも、後半はろくに話もしなかったのだが。そんな事を思いつつ、美由は洗車の後片付けをしていた。
重苦しい状況を作り出したのは、間違いなく自分の責任だ。けれども――心の何処かで、敏行の側の責任を追及しているのも事実だった。少しくらいは、此方の想いを察してくれても良いのに、と――。
それすらも身勝手なのだという事は分かっている。それにしても、敏行が美由の想いとは反する言動をする事が、余りにも多過ぎた。今回は、その極みとも言えるかもしれない。
美由は敏行に、走りの世界の深みを知って欲しくないと思っていた。知れば、自分と同じように辛い思いをする事になると考えたが為に。そしてそれ故に、敏行が走り屋として積極的な発言をする事を、美由は極端に忌み嫌った。だが、それはまだ仕方がないと言えるかもしれない。敏行が別段調子に乗っているわけではない。美由の方が、勝手な感情を抱いているに過ぎないのだから。
しかしながら、今回ばかりはどうか。他意がないからこそ、傷を抉れるのか――。敏行への感情がいよいよ複雑になって来た今になって、間接的とはいえ人には見せられない自らの傷に言及せざるを得ない状況を作り出してくるとは。
このもやもやを払拭するには、走るしかない。敏行の手伝いもあって、いつも以上に磨かれて美しく景色を映り込ませるロードスターを見詰めながら、美由は今宵も幕張の街を走り込もうと決めた。
ふと右手首に目を落とすと、そこには薄汚れたリストバンドが巻かれている。長袖の時はともかく半袖の場合、美由は滅多な事がない限り、右手首のリストバンドを外す事はなかった。勿論、幾つかの替えを持ってはいるが、今付けているのは汚れても良いものなので、お世辞にも綺麗とは言い難い。外向きにはワンポイントのお洒落と思ってもらえるように、綺麗なものも幾つも所持しているのだが、水を使う仕事をしている時は、リストバンドなど邪魔である。それでも、外す事は出来ない。彼女にとっては、あり得ない事なのだ。
――どうして美由は走りの世界に没頭するようになったのか?
――どうして美由は走りの世界から足を洗う事が出来ないのか?
その答えがリストバンドの下にあると言っても、過言ではない。けれども、それは人に知られるべき事ではない。それが、自分の想い人であるのなら、尚更の事――。
――だが、嘗て一度だけ、このリストバンドの下を人に見られた事がある。
車を扱うところであれば、チューニングショップでなくともオイル交換の作業などは珍しくない。世に在る車好きの全てが、車の整備自体にも興味を持っているわけではない。特にオイル交換はそれほど費用を要するわけでもないので、ショップに依頼して来る人間も多い。白昼のガレージ木之下で、工場長の水看は一台の車のオイルの交換作業をしていた。今まで何百回と経験して来たこの作業でミスを犯す事は、先ずない。不意を突かれさえしなければ――。
「工場長ーッ! 本社から電話っすよーッ!」
後方から工員の野呂の呼ぶ声が聞こえ、水看はそちらに気が取られた。その瞬間――水看の腕に、オイルが垂れて来た。
「お……ッと!」
既に冷え切ったエンジンであるし、元より全開走行直後でもなければオイルは触れられないほど熱いものでもないので、逆にど素人が軍手に浸み込んだ熱いオイルに気付かず、低温火傷を起こし得るという事の方が問題だったりする。
「大丈夫っすか?」
予想外にオーバーアクションで手を退けた水看の様子を見、受話器を持ってきた野呂は、怪訝そうな表情を浮かべた。
「ついよ。つい。」
それを受け取った水看は、もう片方の手をひらひらさせて、受け流す。
「ドレンボルト抜ききったとこで大きな声だすから……。」
とはいえ、過剰な反応を示したのは、実は「つい」ではなかった。同じシチュエーションを発端に起こったある出来事が、水看の脳裏に過ぎったからだった――。
ガレージ木之下の世話になり始めてから暫く経ったある日の事。美由はオイル交換をしてもらおうと思い、水看の下を訪れていた。しかし当の水看はその時たまたま仕事が立て込んでいて、美由の車に構っている暇がなかった事もあり、場所を貸してやるから自分でオイルを交換しろと言われたのだった。
美由としても、オイル交換一つ出来ぬ程のメカ音痴というわけでもない。ただ廃油処理が面倒臭かったり、缶一本ピッタリ空になる事が滅多にないとかで、店に持って来てしまった方が何かと楽なのである。自分で買うと結局割高になってしまい、大した得にもならない。
駐車場とは名ばかりの、ひび割れたアスファルトで地面を覆われた入庫車置き場の隅っこへロードスターを移動させ、店内からずるずるとガレージジャッキを引っ張ってくる。ジャッキは重いが、力まずだらだら引っ張るのがラクに移動するコツだ。
「よぉし。」
ラダーレールに前輪を乗せ、エンジンメンバーの下にジャッキの皿を当てる。ジャッキはエアバルブが付いているが、ホースがここまで届かないので仕方ない。面倒だが手漕ぎで何とかするとしよう。サイドシル下部にリジットラックを挟み、地面に敷いたダンボールの切れ端に横になって車の下へ潜り込む。
気温の高い夏の事。渋滞を抜けて来たロードスターのエンジンはまだ結構な熱を帯びていたが、このくらいの温度でオイル交換をした経験は何度もある。美由は手馴れた手つきでオイルパンにレンチを掛けた。
「さーて。潰されてないでしょうね?」
取り敢えずクラッチのセンターが出た為、一旦は場を離れても問題なくなった水看は、美由の様子でも見ようとリフトを離れた。結構暑いし、一台どかせて中でやらせてやっても良かったかと少し反省したのである。
駐車場ではケバケバしい色のロードスターが前輪をジャッキアップされていた。バンパーの下からだぶだぶツナギにでっかいブーツというコケティッシュな足が見えている。
「言ったとおりウマもちゃんと使ってるか。よしよし。」
きちんとした安全意識に満足すると、水看は車の近くにしゃがみ込み、奥の方でもぞもぞ動いている美由の頭に向かって声を掛けた。
「おーい。中に烏龍茶入れてあるらしいから、後で来なよ。」
「あっ! ……と。……あぁ、うん。判った。すぐ行くよー。」
返事の前に美由が妙な声を上げたので水看は下を覗き込んだ。
「どうしたの?」
「何でもないよ。ちょっとボルト外す時に零れちゃった。」
車の下に潜ると、美由の左手、軍手と袖がこげ茶色のオイルでびしょ濡れになっていた。
「あー……。」
「突然声掛けるからぁ。しかもボルト抜く瞬間に〜!」
丁度オイルパンからドレンボルトを引き抜き、オイルが飛び出してくるところで話しかけられたため、ボルトを取り落としてしまったらしい。
「へったくそねぇ。抜くときは一気にいくのよ…って前言ったじゃない。」
「判ってるってば。いきなり話し掛けるからだよ。」
「まぁ、いいわ。結構熱いでしょ。取り敢えず軍手とか換えなさい。袖も拭いて捲くっとかないと。低温火傷って言ってさ……。」
言いながら水看が手を伸ばすと、美由は何故か抵抗した。
「ちょっ……! い、良いよ!!」
「は?」
手を引っ込めると同時に上げたその声が、あまりに喧嘩腰だった為、水看もちょっと腹が立った。急にこの態度は何なの?
「火傷するっつってんでしょ? 新しい軍手あげるから換えなさいって言ってんの!」
「いや……後でやるから大丈夫だってッ!」
今度は目を逸らし、車の外へ出ようとする。どうにも様子がおかしい。
「もしかしてもう火傷してんの? 別に怒らないから見せなさいよ……どれ……。」
「駄目だってば!!」
袖を引っ張って二の腕を見ようとするや、再び手を引っ込めようとする美由。だが今度は水看が離さなかった。無理にでも引っ張って袖を捲くる。一応女の子だし、火傷の跡でも残したら可哀想だ。何を嫌がってるのか知らないが、作業をやらせてしまった手前確認しておかないといけない。
――その時の水看の硬直は、彼女自身が思っているよりも長かったかもしれない。
「……あれ? これって……?」
言いながら、自分が間の抜けた声を上げてしまっている事を後悔した。
――軍手と捲くった袖の間にのぞく細い手首には、幾条もの蚯蚓腫れの様な痕があった。そして、その傷痕の持ち主は、非難と怯えの入り混じった表情で此方を見ていた――。
真夏だというのに、わざわざ長袖を着ている美由。
一年中長袖を着、その下にリストバンドを巻いて生活しているのは何故なのかなどと、水看は考えた事もなかった。
「……あーあ。見つかっちゃった……。」
先に沈黙を破った美由の声は湿っぽかった。今にも雫が零れ落ちそうなほど潤んだ瞳で、無理に笑顔を繕おうとする姿が痛々しい。
「水看さん、力強いからなぁ……。」
「………………………ごめんね。」
やっと搾り出した声は、寧ろ自分の方が震えているような気さえした。
「……全然……、知らなくて……。」
「…………。」
「その……美由って、いつも……元気そうだったし……。」
言わなくても良い事ばかり言っているという事は水看も判っている。だが、声を出していないと頭がどうにかなってしまいそうだった。
子供の頃から知っているという訳ではない。まだ1年ちょっとの付き合いでしか無いし、会うのは夜の幕張か、或いは昼間この工場でだ。知り合って間もないと言われれば、そうかもしれない。
だけど――。それでも、こんな形で知ることにならなくても良いではないか。
「大丈夫……気にしないで……。」
そう言って立ち去ろうとする美由を、水看は袖を引っ張って引き止めた。
「ん? 何……?」
しかし美由は振り向かない。その声からは疎ましさすら感じられる。それも仕方ない事だろう。悪意のない偶然だというのは、言い訳にしかならない。だとしても――。水看は美由を自分の方へと引き寄せる。
「え……水看さ……ん……?」
気付いた時には、美由を抱き締めていた。何故かは判らないが、そうする事が良い様な気がしたから――。
郊外に聳える工場が響かせるけたたましさも、今は耳に入らない。聞こえるのは美由の鼓動と、僅かな嗚咽だけだった。
「……ゴメンね……。」
そして一言、謝罪を述べる。許しを請おうとしているわけではない。ただ、自分なりに疵を抉られる痛みは知っているつもりだ。それ故に――。
初めは戸惑いを見せていた美由だが、やがて何処かホッとした様子で水看の腕の中に収まった。
「………うん………良いよ………。」
「…………。」
ほんの少しだけ、右手首の疵が疼いた気がした。しかしその感覚に、美由は顔を歪めはしない。
あの日の出来事は、事ある毎に美由の脳裏を過ぎる。とはいえ、美由にとってそれは嫌な記憶ではなかった。
確かに、腕に刻まれた幾多もの疵を見られたくはなかった。自分から見せる事など、絶対にあり得ない。ならば逆に、あの時偶発的に水看に疵を見られてしまった事は、良かったのかもしれないと、今となっては考えている。
正直、水看が自分の気持ちをどれほど理解してくれたのかは分からない。それでも、ひた隠しにして来た手首の疵を隠さなくても良い人間に、水看はなった。誰にも明かせないと思っていたこの疵を見て、受け入れてくれた人が居た。――それは十分感謝に値する事だった。
そう、疵に関わる記憶が蘇って、その箇所が気になったに過ぎない。疼いたとはいっても、真に苦痛を感じたわけではない。なのに――ピカピカに磨き上げられたボディに映り込んだ自らの表情は落ち込んでいた。
――だからこそ、と言うのは我侭だろうか?
「どうして敏ちゃんは分かってくれないんだろう……。」
洗車の片付けをしていた事も忘れ、美由はいつしか立ち尽くしていた。バケツを持つ右手に力を込めつつ。
敏行に手首の疵の事を知ってもらいたいと思っているわけではない。それならば、敏行が水看と同じように自分の持つ痛みを理解してくれるようにと望むのも筋違いだ。そこまで行かなくても良い。ただ、自分の気持ちを逆撫でさえしてくれなければ、自分はもっと平静で居られるのに――。
好意故の身勝手な想いは、美由に怒りの感情さえ抱かせる事もあった。
もう夕刻か――。ビルの隙間から見える夕陽に目を向けながら、美由は思った。ビルの陰と夕陽の光輝のコントラストが美しい。見慣れた街並みに毎日訪れる光景なのに、その様は日毎に異なる。今日のような綺麗な夕焼けは、年間を通してもそうそう見られるものではない。見蕩れるようにして再び立ち尽くす美由は――苛立ちを増していた。自分が落ち込んでいる時に美麗なものを見せられて、美由は感情を逆撫でされているかのように感じていたのだった。
同時刻、水看は稀にしかない休暇を、15号線東端の先にある道の行き止まりにレガシィで乗り付け、自らは防波堤のコンクリートの上に腰掛けて、持参した水筒に入れて来た不味いコーヒーを啜りながら謳歌していた。窓を全開にして大音量で掛けてある車のラジオからは、聞き慣れた女性DJの声が軽快な調子でトークを繰り広げているのが聞こえて来る。内容に大して耳を傾けているわけでもないが、彼女なりの休日の過ごし方は、水看に心の安らぎを与えてくれる。
ラジオはコーナーの合間で、リスナーからのメッセージを幾つか読み上げているところだった。そんな中の一つが、不意に水看の耳に留まった。
『こないだ珍しく料理をしていたら、鍋で思い切り火傷をしてしまいました。今もまだヒリヒリして、物が上手く持てません。……あらら〜。気を付けて下さいね。うっかりやってしまう事ってあるんですよねぇ。実はこの間、私も……。』
ふと顔を上げた水看は、DJのその先の話を覚えていない。
「…………ふぅ。」
そして一人静かに深々と溜め息を吐く。
メッセージの内容自体は別段大したものではない。ただ、「火傷」という言葉が、先の事件を水看に思い出させてしまったのだ。
「……全く、変な事思い出させないでよね……。」
ラジオに文句を言ってどうするんだと、内心思いながらも、水看は呟いた。
――確かにあの時、美由を抱き寄せた。だが、水看の気持ちは困惑していた。どうすれば良いか分からずに咄嗟にした行動でしかなかった。今ですら美由の疵を知ってしまった事自体に対しては、後悔の念が拭えない。知らなくても良い事を知ってしまった。美由にとっての禁忌を侵してしまったと――。
美由ほど頻繁にその時の事を思い出すわけではない。だが、水看にとってそれは余り良い記憶ではなかった。それだけに、一度思い出してしまうと、頭を擡げてしまうのであった。
「休日くらい、心穏やかに過ごさせて欲しいもんだわ……。」
ラジオからはやや切なげな邦楽が流れ始めていた。何回か聴いた覚えがあるが、陳腐な歌詞で、余り好みではない。しかし、こういう時だけは妙に心に染みるのだから、困ったものだ。聴きながら再び溜め息を吐き、頬杖をついたまま西の空を見ると、暮れて行く夕陽がやけに寂しげに見えた――。