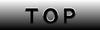― 21.狂乱〜Wahnsinn〜 ―
何だ? この間の話の続きが聞きたいのか? 全く、野次馬根性の旺盛な奴だな。
話してやっても良いが……これから先はあんまり楽しくない話になって行くぞ。その辺は覚悟の上で聞いておいてくれな。
尤も――今の幕張を生きる者なら、知っておいても良い事なのかもしれないな。過去はあくまで過去でしかないとはいえ、現在という時がその先に成り立っているのならば、お前らにも全く無関係なわけではないもんな。
これからお前が聞く事になるのは、そういう話なんだ――。
じゃあ、今日も話してやろう。三年前の話の続きを――。
『あの日現れた一台の車、インプレッサS201。全ては此処から始まった――。』
見上げた空に広がる闇は、普段よりも尚深い。厚い雲が覆い尽くした夜空には、月や星の光を期待するべくもなく、暗澹たる光景が続くだけだった。まだ雨が降り始めていないのが不思議なほどである。
そんな天候の夜ではあっても、幕張の地に足を踏み入れる者が途絶える事はない。尤も、天気の良い日に比べれば、その数は流石にかなり少ないが。周回コース東の空き地で休憩している二人の会話も、その事に及んでいた。
「実に静かなものだな……。こういった幕張も風情があるとは思わないか?」
沙和が軽く顔を上げながら言うと、陶冶も不敵な態度を取りつつもそれを否定しない。
「くっくっく。まぁ、分からんでもないな。普段はもうちょい喧しいか。その意味では、あんま夜の幕張らしくはないけどな。ただ……。」
「ただ……どうした?」
一呼吸置いた陶冶に対して、沙和が静かな様子のままで続きを促す。
「普段と違うっちゅう事は……物騒がしさも漂っとる気がするんや。狭い世界とはいえ、いつ、どないな奴が現れるかも分かへんやろ。或いは今夜はそんな日なのかもしれへんで。」
真面目ながらもふてぶてしさを残した表情で語る陶冶の姿からは、何処か確信めいたものも窺える。
「貴方がそう言うと、本当にそう思えて来るから不思議なものだな……。そのような想いこそが、まだ見ぬ相手を引き寄せるのか……。それもまた、風情があるというものだ。」
一見穏やかに佇んでいるだけの幕張新都心も、彼らにとっては戦いの地であり、それが本来あるべき姿ですらあった。
「くっくっく。それやったら、俺も本望やな。ほな、そんな相手との出遭いを信じて、俺らも出よか。もたもたしとって降られても厄介やしな。」
陶冶が自分の車に乗り込むと、沙和も黙ってそれに続く。そして暫しの間の後、二台はゆっくりと周回コースへと出て行く。今、この場所の筆頭に挙げられる二台のエキゾーストノートは、他の者達を震撼させるに足るものであった。
やがて抱える量に耐え兼ねた雨雲は、大地に無数の水滴をばら撒き始める。淑やかな雨は絶え間なく降り注ぐ。その内に幕張の街をすっかり濡らしてしまった頃になっても、NSXとGTOはまだ周回コースを巡り続けていた。とはいえ、ウェット路面での走行は普段よりも神経を使う。沙和はやや疲労感を覚え、そろそろ一息入れたいと思い始めていた。
――だが、それは暫くお預けとなる。
遥か後方から迫る光に気付いた瞬間、降り頻る雨音も自車の咆哮も一切耳に入らなくなった。直感で悟る。今、自分達は徒ならぬ空気を纏った車に出遭おうとしているのだと。
「……関口の予言は的中か。迫り来るは恐怖……。されど、抗わぬわけにも行くまい……ッ!」
沙和は振り返る事もせず、アクセルを踏み込む。メカチューンのC30Aは天井知らずに高回転まで吹け、パワーを紡ぎ出す。それに併走していた陶冶も、負けじとGTOに搭載されたユニットである6G72に鞭を入れる。唸りを上げた二台の轟音は、この地では全てを押さえ込む力があった。
しかし、今真後ろに付けた見慣れぬ車は、外つ国からの使者。幕張の地のみで適用されるローカルな常識が通用する相手ではない。つまりは、幕張では最強と称される二人も、この車を駆る者にとってはそうではないかもしれないという事である。
「…………ッ!」
言葉を発する事もなく、いや、発する事も出来ずに、沙和はただ強くハンドルを握り、無心にアクセルを踏み付けていた。NAと云えども、極めて高レベルなチューンの施されたNSXは、性能的にもこれまで四天王のメンバーを相手にする時以外で部の悪さを沙和に感じさせる事は先ずなかった
「……だが、それもあくまで限られた世界での話か。こんな瞬間を迎える事を常に心の何処かで期待していた筈なのに、いざその時が訪れると、楽しむ余裕など感じられぬものだな……。せめて雨でなければとも思うが、それも言い訳に過ぎぬか……。」
ミッドシップという均整の取れたレイアウトは、スムーズな動きを可能にする代償として、ナーバスさを伴う。その上にパワーを上乗せされており、更にはウェットコンディションと来れば、もはや綱渡りの走行である。高い技術を持つ沙和だからこそ辛うじて操れているものの、有利な状況とは程遠い。常に冷静さを保っている沙和の表情も、今回ばかりは穏やかではない。ハンドルを切る度にリヤが持って行かれそうになり、背筋が凍る。ストレートセクションの多いコースにも拘らず、車体が完全に直進している時間は極めて短く感じられる。
「一歩間違えればクラッシュの危険と隣り合わせだが……かといってアクセルを抜けばこの車はあっという間に闇の彼方へ消えてしまい――そしてそのまま二度と出遭う事はないかもしれない。そうなれば私はずっと後悔し続けるだろう……。たった一台の車、しかしそれは掛け替えのない車。相手の素性など知る筈もない。それでも、この地でこの時間帯に出遭い、そして自分にこれだけの感情を抱かせたとなれば、思い入れる理由としては充分過ぎる……。躱されてなるものかッ!」
距離的には僅かな差だが、雨による視界の悪さも相俟って、インプレッサの姿は今にも消え入りそうだった。そして、両手で握り締めていたハンドルが、一瞬ぶれる。
「くッ…………!」
それは、本当に僅かなぶれ。傍から見ればミスしたとは分からないような、微小なタイムロス。
だが、今の状況下でのそれは致命傷となり得る。インプレッサは愚か、共に走っていたGTOまでもがNSXと一気に距離を空ける。
それを見た沙和は、ギリギリの状態で保っていた緊張の糸が切れた。ストリートレースは一見、終わりが無い。
その気があらば燃料の続く限り、永遠に走っている事も出来るように見える。
だが、見方を変えればゴールが無いという事は、勝機の見えない戦いに延々と挑んでも無駄であるという事でもある。
腕もパワーも相手の方が数段上と見てほぼ間違いはない。おまけにヘビーウェットでMRである。
先行する二台が比較的ストレスフリーに行える動作も、此方にとっては細心の注意と繊細な操作を要求される。
疲労感も彼らとは比べ物にならない。一瞬の無理が勝利を齎す事もあるクローズドコースではないのだ――。
もはやアクセルを踏み込む意志を無くした沙和は、力なくNSXを脇へと停める。
雨音を掻き消すエキゾーストノートは、あっという間に遠ざかって行った。
「頼むぞ、関口……。貴方のGTOなら、この雨の状況下でも私よりは善戦出来る筈だ……。」
今の私達に追える相手ではなかったのかもしれない――。そんな想いを振り切るように、車を降りた沙和は、尚も走り続ける陶冶に一縷の望みを託した。
「おいおい。藤井の奴、離脱しよったんかい……。こんな奴相手に孤軍奮闘やなんて、ちょいときついで……。」
離れたNSXをバックミラーで確認して、陶冶は顔に笑みを浮かべた。とはいえ、それは彼がいつも浮かべている不敵な笑いとは違う。窮地に追い込まれた者が浮かべる、苦しみに満ちた笑みである。陶冶は紛れもなく必死で逃げているのだが、その様を嘲笑うかの如くに後方の光はピッタリと付けて来ている。
超重量級モンスターのGTOにとって、ウェットコンディションは願ったり叶ったりである。約1.7tにも達する車重とフルタイム4WDは、殊に安定性という面では過剰なまでに優れている。普段は足枷となる事の方が多いその性能が有利に働く、またとないシチュエーションである。だが、それでも陶冶の笑みは不敵なものにはならない。
「くッ……! 抜かせるかッ!」
周回コース北東の交差点で、イン側に差し込まれそうになった陶冶は、強引に被せるようにしてその隙を塞ぐ。その際に、朧げながら相手の車種が確認出来た。
「……インプレッサ……かいな。それにしちゃ、少々速過ぎるんとちゃうか……。」
インプレッサもGTOと同じく4WDであり、しかも車重は圧倒的に軽いので、動力性能においてはインプレッサの方に部があるのは当然である。しかし、追随して来るこのインプレッサの速さは、それだけで説明出来るものではない。陶冶のGTOの心臓部に据えられたV型6気筒3リッターツインターボの6G72は、既に500psを優に超えるパワーが叩き出せるまでにチューンが進められている。そのGTOに、インプレッサは直線でも同等の、いや、それを凌ぐスピードで迫って来ている。インプレッサであると認識する自分の視覚を疑いたくなるほどだ。
「……結局、人はこういう事でもない限り、世間の広さを思い知る事は出来へんのかもしれんな。横綱相撲を取り続けて来た俺にとっては、久しく味わってなかった戦況や。こうも簡単に窮地に追い込まれるとはな……。」
陶冶は心底苦々しい表情をする。例え、どれほど認めたくなかったとしても、相手との車の性能差、そして技術の差は、ある程度走れば大凡の見当は付く。後方を走るインプレッサと比べて、陶冶は双方において及ばないという事を、今この瞬間にもひしひしと痛感させられているのである。
「それでも、諦められへんで……。四天王の……いや、走り屋としての意地故になッ!」
テクノガーデンの交差点を抜け、駅前ストレートへ入る。1km以上続く直線だが、道幅は二車線と狭い。陶冶は後方の動きを確認しながら、前に出る。強引なブロックをするつもりでそうしたわけではない。それにも拘らず、インプレッサが此方を追い抜こうとして来る気配は感じられない。――アクセルを抜いている? いや、そうとしか考えられない。今までの走りを見れば、インプレッサが直線でオーバーテイクを掛ける事も充分可能なだけのパワーを備えている筈だ。なのに、そうしない。
「ちッ……! 舐めおって……ッ!」
もはや自分は全力を持って相対する必要はないと判断されている。それはどうしようもなく悔しく、腹立たしい事だったが、止むを得ないという事も陶冶には分かっていた。だが、諦めない。そう、彼が言うように、走り屋の意地があるのだから。まだ抜かれたわけではない。それなら、悪足掻きでも良いから、勝機を探って行こうではないか――。
彼は相手の動きを封じるような走りを得意とする。自分から仕掛けるとすれば、得意とする分野に賭けるしかない。それがこの相手に通用するかどうか、そこまで考える余裕は今の陶冶にはなく、ただ直感的に行こうと決心したのだった。
「行くでッ! 覚悟せぇッ!!」
ストレートエンド、海浜幕張公園の交差点への進入。陶冶は車体をインプレッサの真ん前に持って行く。
そこから、本来ならばまだアクセルを抜かないような早い段階で、ブレーキを踏み込む。
前のGTOが減速した事で、当然インプレッサもそれに合わせて減速を余儀なくされる。
タイミングを狂わされたインプレッサは、そのままコーナーもスピードの乗らない状態でクリアせずを得なくなる――。
それが陶冶の作戦であり、今まで何度もこの方法を成功させて来た。
だが、絶対的な力の前には、小細工を弄しても効果はない。
「な……ッ! んな、アホな……ッ!?」
思い描いていた通りのラインに乗せ、アクセルを踏み込み立ち上がろうとしていたGTOの脇に捩じ込んで来た影。初めて前方の視界に入ったインプレッサの姿は、狂おしいまでの勢いで加速して行く。陶冶の妨害など物ともせず、インプレッサは立ち上がりで勝負を掛け、あっさりとGTOを抜き去って行った。前に立ちはだかるもののなくなったインプレッサは、まるで渋滞を抜けた後のように気持ち良さそうにエキゾーストノートを高鳴らせつつ、速度を増して行った。その様に陶冶は愕然とし、走り去るインプレッサの姿をただ呆然と眺める事しか出来なかった。
それからどれくらいの時間が経ったのだろうか。気付くと後ろには沙和のNSXが停車しており、沙和本人の方は自失していた陶冶を呼び覚ますかのように、窓ガラスをコンコンと叩いていた。
「ああ、お前か……。」
まだ意識が戻り切っていない様子でそう言ってから、陶冶は徐に車を降りた。
「私の所まで一周して戻ってくる事は出来なかったな……。」
静かに口を開いた沙和だが、内心は非常に悔しがっている事が、陶冶には判った。そしてそれは陶冶自身も同じである。本来なら沙和の言葉に皮肉の一つでも返したいところだが、今はそんな気分になれなかった。
「……せやな。俺としては、お前が離脱してからえらく長く走ってたつもりでおったが、実際には半周ちょい行った所で千切られてしもうたんやな……。情けないもんやで。」
先までの記憶を思い返した陶冶は、顔を上げてインプレッサが去って行った方角を見たが、もはやその姿はおろか音も聞こえる筈はない。雨音だけが静かに夜の闇に響き渡っていた。
「あれは……インプレッサだったか? 私は一瞬しか視界に捕らえられなかったので、確証はないが……。」
沙和の問い尋ねに、陶冶は硬い表情を保ったままで答えた。
「ああ。旧型インプレッサやろ。厳めしいエアロ着けとったけどな。確か、いつぞやに出た限定車やなかったか? ……まぁ、外見は元よりあの走りは、限定車である事よりも遥かにレア物とちゃうか……。」
しっかりと目視出来たのは、陶冶も最後に抜かれた際の一度でしかない。だが、車の外見は確認出来ずとも、その様は二人の脳裏に強烈に焼き付いている。正に人並み外れた、未知のレベルの走り。今までこの幕張という場所で、あれほどの走りを目にした事はなかった。
「あの車、幕張の者ではあるまいな?」
尋ねる沙和の言葉からは、幕張の者であって欲しくはないという願望も察せられる。対する陶冶も、その願いを支持する答えを返す。
「そうやと思うで。それに、もし此処の奴やったら、四天王やなんて騒がれて好い気になっとる俺らは、ただの馬鹿やないか。底辺の連中が内輪で勝手に盛り上がってただけって事になってまうで。」
そして陶冶は軽く笑ったが、それも自嘲的で力ないものだった。続く言葉を言う頃には、その笑みもすっかり消えていた。
「……せやけど、例えどっか別の場所からの奴やったとしても、俺らが大海を知らんかった事に変わりはあらへんか……。ローカルチャンプの座が崩れへんかったとしても、その事に意味はない。いや、寧ろ自分の座っとる玉座が偽物やったという事を知らされてしもうたんや。もう、そんなもんに興味は持たれへん。真の玉座を捜し求めたくなるんが、人間ってもんやろ。」
話を聞いていた沙和は、静かに問う。
「それでは、貴方は新しい座を求めて行くのだな?」
「お前は、そうせぇへんのか?」
すかさず訊き返されて、沙和は首を振った。
「……愚問であったな。私達は今までずっとそうして来たし、そしてこれからもそうして行くのだろう。終わらない旅の途中に在りながら、いつしか先へ進む事を忘れていた……。高みを目指す事を止めてしまえば、それは走りを終える事にすらなりかねない……。幕張という場所で息衝いておきながら、実は私達こそが最もこの場所に相応しくない人間へと成り下がってしまっていたのかもしれないな……。」
沙和の言う通り、こういった出来事は在り来たりなのものである。より速い者との出遭いとは、恒常的に起こるものであり、同時に走りに熱中する者達の多くが期待する事象の一つであろう。
しかしながら、その内容に関しては、在り来たりとは到底云えないものだった。インプレッサという車のポテンシャルから考えられる範囲を大きく上回る絶大なるパワー。そして幕張でトップと謳われる者達でも全く太刀打ち出来ないまでの根本的な速さ。次元の違う走りというものを見せ付けられた。いや、既に人知を超えているといっても過言ではないかもしれない。
『――そいつの速さは驚異的だった。幕張最速と呼ばれた四天王の一角の二人ですら見た事のない、未知の速さ。
出遭った二人は、ただ圧倒されるばかりだったそうだ。
だが、だからといってそのまま縮こまってしまうような連中じゃない。未知の力に、あいつらはあっという間に魅了された。
そして、その力を超えてみたいと願うようになったんだ――。』
それから数日が経過して、白いNSXと碧のGTOはすっかり幕張で噂となっていた。連日のように走り込む姿が目撃されている事は元より、その様からは鬼気迫るものが感じられ、走り屋達の間で怖れられるようになっていた。
S2000を駆る孝典の知り合い、江もそんな中の一人であった。
「歯が立たないのは分かってたけど、それにしてもあれは驚いたぜ。
一気に食らい付いて来たかと思ったら、その後幾らも行かない内にちょっとの隙間から抜かれてな。
本当に狭い隙で、そこから抜いてったってのは流石ではあるんだが、あれはちょっと強引だったぜ。
一歩間違えれば、クラッシュもあり得たぞ。」
語る江の態度には、怒りの感情も含まれているように見える。一方の孝典は、意外といった様子でそれを聞いていた。
「本当か? 関口ならともかく、藤井がそんな走りをするなんな……。」
返り血を浴びぬ純白の暗殺者――。沙和個人としては、そんな通り名が付いている。瞬く間に相手の背後へと忍び寄り、そこから虎視眈々と抜き所を探る。決して無理なオーバーテイクはしない。確実に抜けるタイミングが来るまで、静かに相手の後ろを走り続ける。その代わり、僅かな隙でも見付けたなら逃さずに確実に仕留める。相手が抵抗する間もないほど、一瞬にして華麗に。ある意味、極めてクリーンな走りを身上とするのが、沙和という走り屋なのである。
それ故に、孝典が驚くのも尤もな事だった。
「俺としても、気になるところだな……。何かあったのかもしれない。一度、話を聞いてみないとな。」
真面目に言う孝典に対して、江は突慳貪に言い放った。
「もうちょっとは他の車とも合わせる事もしてくれって言って聞かせといてくれよ。それが出来ないような奴じゃないんだしな。」
怒りと悔しさを織り交ぜた様子に、孝典は苦笑するしかなかった。
愛機のRX−7で周回コースに出た孝典は、普段よりも車の台数が若干多く感じた。とはいえ、目新しい車はないように思える。孝典も実際に知っていると公言出来るほどに集う車を知っているわけではないが、やはり狭い世界であるが故に、新参者でなければどの車も大なり小なり見覚えがある。それでも、ある程度纏まった台数を見るのは孝典も久し振りであったので、何処となく違和感も感じた。
「あいつらの出現を聞き付けて、血気盛んな連中が集まって来たか? ……確かにいつもより殺気立ってるか……。」
孝典も四天王の一人に数え上げられている人間である。他の走り屋からすれば、陶冶や沙和と同一の対象とみなされる。その為、流している最中に出遭った車の中には、孝典に対して挑戦してくる者もあった。勿論、それらの者の腕では孝典に敵うべくもないのだが、それでも道を譲ろうとしないのは、それだけ彼らが好戦的になっている事の証拠だろう。
そして、やがて孝典は現在最も高い戦闘意欲を持っているであろう相手と出遭う事になる。尤も、当初思っていた相手とはやや違っていたが。
「……関口か。まぁ、お前でも同じ事だ。」
孝典は沙和を探して走っていたし、陶冶と会った場合でも話を聞きたいだけだった。だが、陶冶がその事を知る筈もないし、何よりこの場所で双方とも車に乗った状態での邂逅となれば、こうなる事も止むを得ないと云えよう。
「逃げるか……。そう来ると思ってはいたけどな……ッ!」
視界にGTOの後姿が現れたと思うや否や、赤い灯火は猛然と遠ざかり始めた。それを見た孝典は、やれやれといった顔をしながら、アクセルを開けた。陶冶とは走り慣れている。――だが、今日はいつも通りとは行かなかった。
「ん……? こいつは……。」
パワー勝負の駅前ストレート。孝典のRX−7は、陶冶のGTOと比べても遜色のない加速をする筈だったのだが、既にアクセルペダルを底まで踏み付けているにも拘らず、GTOの姿は離れて行く。RX−7の調子は万全である事を考えれば――。
「関口の奴、パワー上げたな。しかもこいつは、圧上げとかのレベルじゃないぞ……。」
重量面での不利を補う意味もあって、陶冶のGTOは元来かなりの馬力を誇っていたが、今孝典の眼前で加速して行くGTOの姿からは、それを遥かに上回る力を感じさせる。
こうなって来ると、孝典も話を聞くという本来の目的などに構っては居られない。走り屋として、みすみすと相手に逃げられてしまったり、不利な状況に晒されたからと相手にあっさり不戦勝を献上してしまっては、面目丸潰れである。
ストレートでは不利だが、RX−7にはGTOとは対照的に軽快さというメリットがある。GTOの方は強大なパワーによって、以前にも増してコーナーで苦戦を強いられる。そこを突き、特にコーナーの進入に掛けて、ギリギリまで攻め込んで差を詰める。それでも、そのお陰で何とか食い付いて行けているといった程度で、前に出る事は出来ない。落ち着いた性格の孝典も、表情に焦燥を滲ませるようになって行った。
そして事態は更に孝典を逼迫へと導いて行く。
「くッ! 今になって現れるかよ……ッ!」
合流して来たマシンは、純白のボディを纏う。孝典が当初捜し求めていた相手の、沙和である。しかし、今の孝典が尋ね人を見付けたと歓ぶ筈もない。この状況では、戦火を激しくする火種が増えただけでしかないのだから。
しかも、その火力は凄まじかった。それは更なる力を身に付けたGTOを捉える事が出来るほどのものであり、そして同時に孝典とRX−7にとっては辛いものであった。
「おいおい……。お前ら、連れ立ってパワーアップなんかしやがってッ!」
今までの沙和のNSXは、相当なハイチューンとはいえNAのままであったので、パワー勝負となると高速域では加速が頭打ちとなり、ターボ車と比べれば分が悪かった。しかし、今のNSXは違う。それはハイパワーを誇る陶冶のGTOと同等のスピードを叩き出している事からも明らかである。ブローオフバルブ等、ターボ車特有の音が聞こえるわけではないが、恐らく沙和のNSXは――ターボ化されている。
「全く。大幅なハイパワー化だのターボ化だの、よくもまぁ、そんなあっさり出来るもんだな!」
この状況下では、こんな見当外れの皮肉を言うのが精一杯だった。コーナーで辛うじて食い付いて行けているだけで、ストレートでは此方の方が劣勢なのは否定し様がない。寧ろ孝典であるからこそ、性能面での不利を背負いながらも此処までの走りが出来ているのであろう。そして、幾ら孝典であるとは云えども、限界がある。やがて取り返すことが出来ないほどの差――実際の距離は然程でもないが、この二人を相手にしては決定的な差を付けられて、孝典はとうとうアクセルペダルから足を離した。苦り切った表情を浮かべながら。
走り終えた孝典は、周回コース東の空き地へと戻った。しかしそこには、まだ陶冶も沙和も居なかった。周回コースの方を気にして見ると、まだ二人とも走っているようだった。
「俺と走っただけじゃ、物足りないってか? 大した気力だよ。」
本人を前にしないでは、ただの独り言でしかないが、またもや苦言を呈する。それだけ今回二台に千切られた事が悔しかったのだろう。
それからもう暫くして、ようやく二台が空き地へと帰って来た。車を降り立つ陶冶と沙和。その姿を見た孝典は、一瞬息を呑んだ。それは、陶冶の目付きが感じさせる狂わしさも、沙和の瞳に窺える冷淡さも、孝典が知る普段のそれよりも度合いを増していたからだった。
「くっくっく……。よう付いて来れたなぁ。流石は歌野やで。」
不敵な笑みと共に放たれる皮肉。しかしそれは、いつもより辛辣に響いた。
「そりゃどうも。俺も我ながら頑張ったと思うよ。しかし、どうしたんだよ? 今になって急に大幅な性能強化だなんて。」
回り道もせず、孝典はすぐ二人に尋ねた。だが、沙和は答えをはぐらかす。
「別に、今になってという事もなかろう。速さを求めて行く上で、車の性能を上げる事は至極当然ではないか。それがたまたま今だったというだけの事だ。」
淡々と語る沙和の様子からは感情を読み取れないが、それが真意ではないと察するのは、孝典でなくとも容易だろう。
「陶冶と二人、申し合わせたかのようにしてか? しかも、最近はかなり頻繁に牙を剥いてるそうじゃないか。
それが原因で最近の幕張が殺伐として来ている事は、お前らだって気付かない筈もないだろう。」
食い下がる孝典に、陶冶は再び不敵な笑みを返す。
「くっくっく。やっぱ歌野は煮ても焼いても食われへんな。しゃあない。説明したろやないか。」
口を開く事を決めた陶冶に対して、沙和はまだ渋った様子を見せていたが、やがて沙和も加わりつつ、孝典に事情を明かす。切っ掛けとなった、インプレッサS201の事を。
「……あれだけの車と乗り手。そうそう居るものではない。……いや、私達はあのレベルの走りが存在する事自体を知らなかったのだ。」
思い返す沙和の口調は消え去りそうなほど静かで、しかし重々しさを感じさせるものだった。
「そうか……。陶冶や沙和にそこまで差を痛感させるとは、本当に並外れた走り手だったんだな。」
一通りの説明を受けて、先ずは相槌を打った孝典だったが、沙和達の行動には納得が行かないようだった。続く言葉で、その想いを言い表す。
「だが……それにしたって、二人とも余りに急激過ぎやしないか? 焦ったって、何も得する事はないだろう。それに、藤井。お前はNAで戦い抜くのを美徳としていたじゃないか。それを排してまで、力を欲する必要があったのか?」
諌めるような孝典の言葉に、沙和は自嘲的な笑みを薄く浮かべながら答えた。
「私とて、出来るものならNAに拘り続けたかった。自らの操作と完全に同調するかのようなダイレクト感や、限界を知らぬかの如く回り続ける突き抜ける加速感。いや、低回転でのトルク不足や、パワーバンドの狭さすら、私は好きだった。車とは、速さのみならず、フィーリング面での悦びというものもあるのだからな……。だが……もはや、そんなつまらない拘りに固執する余裕はなくなった。NAで戦う事が美徳? 違う。それは生温い環境下でのみ許されていた甘えでしかない。そんな時期はもう過ぎたのだ。私は知ってしまった。今居る場所よりも、遥かな高みが存在する事を。その領域に達する事を、私は望む。その為ならば、己の美徳を捨て去るなど、造作もない事だ。」
無感情な印象を与える沙和だが、述べる言葉の節々からは、急いて気を揉んでいる事が分かる。
「……お前なら大丈夫だと思う上で、敢えて言わせてもらうが、自らの技術の程度を思い知ったなら、自分に相応しいレベルのマシンってものも弁えられるだろう。危険と常に背中合わせの行為と云えども、いや、だからこそ可能な限り危険を回避するように努力すべきだ。真にスピードを追い求めている奴は、死にたがりなんかなじゃない。リスクを承知した上で、この世界で生き抜いて行く事こそが、至上目的とも云えるんじゃないか?」
反感を買うであろう事を分かっていて言った言葉だったが、その予想は見事に的中する。
「くっくっく。それはな。当事者でないから言える事や。お前も出遭えば分かる。奴は、全てを擲ってでも追い掛けてやりたいと思うだけの力を備えとるんや。……ま、お前は今まで通り、のんびり走っとりゃええんとちゃうか? 実際に会うとらん奴に強制したかて、意味あらへんからな。好きにしたらええ。お前の如何に拘らず、俺らは行く。お前の知らへん領域へな。」
それは決別の意味に近いのかもしれない。その気がない人間は相手にしない。例え、それが今までの仲間であったとしても。そんな風に陶冶の言葉を取った孝典は、黙って聞く事しか出来なかった。
それと同時に、孝典にはもう一つ気になる点があった。目の前の二人のように、速い相手に触発される気持ちは良く解る。だが、果たして彼らのように極端な入れ込みをするようなものなのだろうか。
元より、今はそんな想いを吐露出来るようなシチュエーションでもない。
「……せいぜい死なないように気を付けろよな。」
静かに言い放った孝典の言葉に、沙和が踵を廻らしながら答えた。
「死んでなるものか。あのインプレッサと再び巡り合い、そして前を走るまでは、死んでも死に切れぬというものだ。何としてでも走り抜いて見せる。心配には及ばぬ。」
続いて陶冶もGTOのドアに手を掛けながら言う。
「……藤井の覚悟はなかなかのもんやで。勿論、俺もばっちり臨戦態勢を敷いとるがな。まぁ、気ィ付けて走れや。お前かて、気合い入れて走らな、すぐに撃墜されてしまいかねんで。」
そして沙和のNSXと陶冶のGTO、二台のエキゾーストノートが再び幕張の地に激しく木霊する。それに気付いた空き地に居合わせた幾人かの者達も、後を追うようにして周回コースへと出て行く。取り残された孝典は、途端に人気のなくなった空き地で、暫し惚けるようにして立ち尽くしていた。
「……これが、幕張の本来在るべき姿なのか……?」
自分でも不思議に思うほど、孝典は恐れにも似た危惧を抱いていた。
『――確かに俺は力を欲する事を危惧した。だが、力を求めているのは俺も同じだった。そう、俺もまた魅了されていたんだ。出遭った事すらない、S201という車に。
そして、俺は本当の危険性などには気付いていなかった。
それが本当に悲劇を生む事になってしまうなどとは、思いもしなかったんだ――。』
それとは別の日の事。沙和はいつものように幕張の街を走っていた。
目的であるインプレッサS201とは出遭えていないが、追い来る車には事欠かない。
今も一台の車に追われている最中だった。今度食らい付いて来たのは、FDであろうか――。
一瞬バックミラーを確認はしたが、相手の車種に関してそれほどの興味はない。
付いて来られなければそれまでの事だし、速いのであれば強制的に知らされるのだから、先ずは走りに集中すれば良い。
ある程度合わせて走ってみたが、やはり大した事はないようだ。
必死に追おうとしているのは分かるが、それだけ余裕がないという事でもある。
「……次で終わりだ。」
ぽつりと呟くや、沙和は見浜園の交差点へ向けて猛然と加速し始めた。見も知らぬその他大勢にくれてやるような燃料は、生憎持ち合わせていない。優に500馬力はあろうかという強大なパワーを、極太のリアタイヤが地面に余すところ無く伝達する。
ターボ化は正解だった――。そう思った。例えそれが自分の拘りやら美徳やらを犠牲にして得たものであっても。
現にトラクションを求めて巨大化した今のタイヤでさえ、既に腰から危うい感じが伝わってくる。頂付近の狭小な回転域での伸びは捨てたが、中回転域のもどかしさが、完璧に消え去っている。何よりもこの圧倒的なトルク。大出力に麻痺した沙和にさえ、時折恐怖心を呼び起こさせるほどの加速感である。
弾かれたように加速を始めるNSXに、慌てて追い縋ろうとするRX−7。もともとアウトプットが比較にならない上、
乱暴なアクセルワークが車体の挙動を乱し、差は開く一方だ。
ドライバーが募らせる不安感を他所に、NSXは既にコーナリングを開始している。
ここは唯一、周回コース内で鈍角。スピードは乗る。
進路が定まらないままNSXに続いて海浜幕張公園の交差点に進入したRX−7は、
前輪をスリップ気味のまま旋回動作に入ったが、コーナリングを終える辺りで逃げたフロントを曲げ切れずに、
見浜園東側の中央分離帯に軽く接触した。反射的にドライバーはステアリングを更に深く切り込んでラインを修正しようと試みるが、
まだ後輪がグリップ仕切っていない事まで頭に入ってはいなかった。突然に逆方向へ回頭し始める車体。
「…………!」
ステアリングを咄嗟に離すが、セルフカウンターが間に合わない――。
後方からの小さな衝突音に、室内鏡にちらと目をやると、RX−7がフロントから斜めに、車道と歩道を隔てる縁石に乗り上げて跳ねているところだった。前方に突き出したエア・カットフラップが、縁石で車体を蹴り上げ、植え込みの枝が外れかかったフロントバンパーを絡め取る。植え込みに鼻先を埋め、斜めに滑るようにして減速していくRX−7。乗り上げた時に割れたのか、車体の下からは大量のオイルが漏れ出している。
「……またか……。」
感慨なさげに呟くと、変わらず的確な動作でNSXの向きを整える。
この程度のクラッシュも、そう珍しいわけではない。取り立てて騒ぎ立てるほどの事でもない。
遥か前方の幕張海浜公園の交差点まで、周回路で最も長い加速区間に躍り出た沙和は、
スロットルに直結して空を切り裂くNSXに恍惚を覚えながらも、ふと思った。
「……それにしても、最近は事故が多くなった気がするな……。歌野の言う通り、この幕張も殺伐として来たという事か……。」
ただ、その一点だけは沙和も気になった。彼女もこの場所を訪れるようになって長いので、感覚的にとはいえ、
こうした事故が増えて来ているようには感じていた。元より、今の沙和がそこにそれ以上の感傷を抱く事はなかったのだが――。
更にまた別の日。今度は沙和のNSXに加えて陶冶のGTOも幕張を走っていた。
二台が揃えば、追って来る車の数も乗算する。何度引き離しても、また新たな車が食らい付いて来る。
恐らく、沙和と陶冶も後ほんの少し冷静であれば、この状況が如何に異常なのか気付いた事だろう。
だが、彼らも知らぬ内に潮流に飲まれていた。過剰な戦闘意欲に駆られているのは、追う者も追われる者も同じだった。
追い来る者の数が多ければ、その中には速い者も点在する。その車は二台に追い付かれた事に気付くと、猛然と再加速し始めた。
丸目4灯のテールランプの間に輝くのは、「R」のエンブレム。――32Rか。
車そのもののポテンシャルも去る事ながら、今前方に在るその車は、チューニングの度合いも高そうだ。
並み居る走り屋の中でも、抜きん出た存在かもしれない。
だが、それに立ち向かうのは四天王の一角を担う二人――。名実共に頂点に君臨する二人、そして二台である。
このGT−Rも、車の仕上がりはかなり良さそうだ。しかし、それを生かしきれるかどうかの差で、速さは如実に変わって来る。
四天王の二人がまだ余力を残しつつ走っているのに対して、GT−Rは既に限界が近い走りをしている事は、
本人達のみならず周囲の目からも明らかだった。
それでも、馬力だけは相当に高い。速度の乗る幕張であれば、それだけでも大きな武器となる。
多少引き離されたところで、一気にストレートで巻き返して来る。
「くっくっく……。ええやないか。速くなる為の手段は、何も技術を身に着ける事だけが全てやない。
それを補う為に力を手にするっちゅうのも、大いにありやろ。さぁ……その力で追い詰めて来いやぁッ!」
如何にも楽しそうに笑う陶冶。超重量級マシンのGTOを速くする手法と、本人の嗜好も相俟って、
陶冶はかなりのパワー主義者であった。故に、このGT−Rのようなマシンは彼の好むところでもある。
小細工なしの、単純明快な力。そこにどんな異論を差し挟めると言うのか。
「この世界にはお前よりも、そして俺よりも強大な相手ってのが居るんや。せやけど、こうして鬩ぎ合う事で僅かでもその相手に近付ける筈や。
その為にも、せいぜい派手に戦おうやないか! 手加減なんて出来へんでッ! くっくっく……くかかかかかかかッ!」
今までないくらいに高らかで不気味な笑い声を上げると、陶冶は景気良く次のギヤへシフトレバーを入れる。
一瞬落ち込んだ回転は、瞬く間に再びピークパワーへと向かって駆け上がって行く。
四肢は地をしっかりと捕らえつつ、重たい車体をあっという間に高速域へと導き上げる。
例えこのGT−Rの前には霞んでしまうレベルだとしても、陶冶が抱く愛機への信頼は変わらない。
それは沙和も同じだろう。紛れもなく追い詰められている状況であるにも拘らず、二人は一片の迷いもなくアクセルを踏み続けた。
迫り来る恐怖を駆逐する為に。
元より、GT−Rのドライバーがそんな事は気に留めるどころか、知る筈もない。
コーナーでは上を行かれても、それを取り返すだけの力があの車にはある。
だとすれば、GT−Rの方にも諦める理由はない筈だ。
「そんだけ大層なパワーを持っとるんや。多少技術が足りんかっても、卑屈になる事はない……。
お前にその気がある限り、俺らは何処までも付き合うたるでぇッ!」
縺れ始めたこの事態を楽しんでいるその様は、如何にも陶冶らしい。
だが――それでもやはり、この時の陶冶はある一線を越えていたのかもしれない。
インプレッサS201に完膚なきまでにやられ、その為に寧ろ極度の戦闘意欲に駆られていた陶冶と、そして沙和は、
既に“いつも通り”の姿ではなかったのかもしれない――。
テクノガーデンをクリアして駅前ストレートに入ると、バトルの主導権は一気にGT−Rに移った。
凄まじいまでの加速力。北東の交差点からハイテク通の高速S字を経て此処まで来る間に、陶冶達との差はかなり開いていたが、
再びその差が瞬く間に詰まる。また振り出しか――。流石の陶冶も苦笑いを浮かべる。
此方が降りるつもりはないので仕方ないのだが、これでは埒が明かない。
「こいつは持久戦になりそうやな……。集中力が切れた方が負けってわけか……。まぁ、そういう戦いも悪くないんとちゃうか。」
沙和はこういう状況には滅法強い。ならば、自分も遅れを取るわけには行くまい。陶冶は心を決め、ひたすらにアクセルを踏み続けた。
ストレートエンド、幕張海浜公園の交差点が見えて来る頃には、三台はすっかり数珠繋ぎになっていた。
先ずは沙和のNSXがコーナーにアプローチし、すぐ後ろから陶冶のGTOも続く。そこでGT−Rは――勝負を仕掛けて来た。
陶冶達二台が縦並びになり、一車線空いたその隙を突いて、GT−Rはブレーキングを遅らせて飛び込んで来た。
「く……ッ! 来おったなッ………!?」
陶冶がGT-Rの異変に気付いたのは、
相手が差し込んで来た直後だった。レイトブレーキングは結構だが、様子が変だ。幾ら何でも速すぎる。
旋回するには、全くもって減速が足りない。ほぼ同時にその事に気付いた沙和と陶冶は、一旦距離を取るためステアリングを戻し、
直進状態でのフルブレーキングに切り替えた。前方に見える、赤熱するブレーキローターから吐き出される灰色の煙は、
GT-Rのブレーキシステムが既にそれを停止させるだけの能力を備えていない事を物語っていた。
このままでは、コースオフは避けられない――。
陶冶たちが引いたお陰で右側が空く。GT-Rのドライバーは咄嗟にシフトロックを使って車体をそちらへ向けた。
まるで氷上でもあるかのように、右前方を向いた状態のまま滑っていく車体。
そうして殆ど減速のないまま、車体を緩衝材に、ようやく車は中央分離帯の上で停止した。
そのすぐ脇を擦り抜けるように通過してゆくNSXとGTO。三者三様の咄嗟の判断は、何とか誰の生命を奪う事も無く、事を収めた。
それで満足したとばかりに、二台は猛然と加速していく。
「悪いが、有象無象の連中に構っていられるほど暇ではないのでな……。」
「――お前が復活出来るようなら、またいつでも相手したるで……。アイツに遭うまで、立ち止まってるわけに行かんのや。」
あのGT−Rが見せた速さはかなりのものだったとはいえ、それで陶冶達の心が満たされる事はない。
そう、あのS201に再び出遭い、その前を走るまで、彼らの心は渇き続けたままなのだ。
二台は、ウエストゲートの炸裂音を盛大に響かせながら、混沌を深める幕張の闇の中へと消えて行った――。
正面からの直撃は避けられたものの、街灯の鉄柱がセンターコンソール付近までめり込んでいる。
運転座席のショルダー部まで、あと数センチ。事故を目撃して慌てて駆けつけた仲間が、
右のドアを破壊してGT-Rのドライバーを引き摺り出す。フルハーネスで身体を固定していたお陰で、
ガラスの破片による小さな擦り傷以外、目立った外傷はないが、衝突の瞬間首を強く捻ったらしく、その声は弱々しかった。
「やっぱり……バランスを無視して改造るもんじゃないよな……。何とか連中の前に立ってやろうと思ったとはいえ、
無茶なパワーアップをしたもんだ……。靴紐が解けている事に、最後まで気付かなかった……。」
「それだけベラベラ喋れりゃ上出来だ。……ちょっと痛いぞ。」
ハーネスを解き、肩と腿を支えて外に出す。ドライバーは思ったより強く走る痛みに顔を顰めた。顔色もさっきより幾らか蒼白になって来ているようだ。
「……っつ……。ぺ、ペダルが途中で奥に突っ込んじまって……。……こんな所で終われねぇのに……。」
「OKOK……四天王相手に良くやったよ。レッカーとかはこっちでやっとく。お前は取り敢えずノリの車で病院行きな。
今、取りに行ってるとこだからさ。」
「悪ぃな、色々……。」
良く温まった缶コーヒーを差し出し、仲間は最後に一言呟いた。
「ま、死ななくて良かったな。」
それから更に日数が過ぎ、深夜の幕張の恐慌状態はいよいよ顕在化していた。其処此処で勃発するバトル。チューンドカーの哮る声は、途切れる事無く幕張の街に響き渡り続ける。
そして――それに伴って、事故の数も如実に増えていた。中にはかなり大規模なクラッシュも起きた。だが、それでも彼らは走る事を止めようとはしなかった。まるで何かに取り付かれたかのように、ひたすらアクセルを踏み続けるのだった。
あれ以来、孝典は沙和達と会っていない。しかし、彼らを追おうとする者が後を絶たない事は、コースへと出れば出遭う車の殆どに追い立てられている孝典にも良く分かっていた。今も、一台の車を引き離したばかりだった。一旦アクセルを緩めると、孝典は軽く計器類を眺めた。
「……よし。問題ないな。」
指針がどれも正常値の範囲内にある事を確認すると、安心して再び視線を戻した。
実は孝典も今回、RX−7のパワーを少し上げていた。沙和達の行いを危ぶみ恐れる一方で、戦火の激しくなった幕張の地に身を置く上で、生き抜く為に――つまり、勝ち抜いて行く為に、少しでもパワーを上げておきたくなったのだった。数値的には僅かなパワーアップで、どちらかといえばパワーアップを施したという事実で、精神的な余裕を得ようとした意味合いの方が強いが、結局は自分も沙和達と同じで、咎め立てる立場になど全くないのだという事を自らの行動によって思い知らされ、孝典は軽い自己嫌悪に陥っていた。
だが、戦場と化した幕張を巡る路の途上に在るからには、感傷的になっている暇などない。バックミラーにはまたもや意気揚々と迫るヘッドライトの光が照り輝いている。しかし、この度は反応をやや異にした。
「……S2000……江かッ!?」
街灯に映し出された姿をミラー越しに確認して、孝典は思わず口走った。江のS2000である事は間違いなさそうである。しかし、その走りは孝典の知るものではない。異様に速い。いや、正確に云えば、S2000では考えられないほどのパワーを備えている。技術はそれに追い付いていない様で、コーナーでは暴れ回る車体を辛うじて押さえ込んでいる様子である。それでもパワーに任せて、必死に孝典を追って来ている。
「お前もか……。今の幕張は本当にもう、俺の知る世界ではないんだな……。」
対する孝典は、言い様のない不安を感じていた。江に負けてしまうかもしれないという想いもあるが、主たるは扱い切れないパワーに江が食われてしまうのではないかという、幕張が今の状態になってから孝典が抱いていた一番の怖れを、江に感じたからだった。
それでも――孝典はS2000から逃げ続けた。そこまで分かっていながらも、つまらないプライドは孝典の心を占めて離さない。江に抜き去られるのは我慢ならない。負けてなるものか。その想いが、懸念を封じ込んで孝典を突き動かす。自分はどうしようもない愚者なのだと想いながら、アクセルを踏み続けた。全く手を抜かずに走る孝典。
しかし、本気の四天王の走りに、江は追い縋った。ストレートで稼ぎ出すスピードは、孝典のそれをも凌ぐものだった。
「何だってんだよ! どいつもこいつも……ッ!」
自分でも訳が分からないほどに、怒りにも似た焦燥感に駆られ、孝典は声を荒げた。それでも、高い技術力を持つ彼の走りに乱れはない。
一方、猛追を見せている江だが、バトルが進むにつれ、徐々に安定感を欠き始める。オーバースピードでコーナーに突っ込んだり、ストレートでも高速域で揺さ振りを掛けようとしてハンドルを切り過ぎたりして、目に見えて体勢を崩す事が逓増して行った。時には外壁に接触するほどである。もはや江にとっては限界を疾うに越えた走りである。
「もうよせ! 江! お前には無理だッ!」
孝典の方が走るのを止めるのが最善なのだろうが、それが出来ないとなれば、後は江が諦めて降りてくれる事を期待するしかない。身勝手と知りつつも、そう強く願いながら、孝典は走り続けた。
やがて、何度目かの駅前ストレートで、再び最高速バトルが展開される。RX−7の真後ろに張り付き、揺さ振りを掛けるS2000。直線での速さに限って云えば、S2000の方に軍配が上がる。前を行く孝典も、隙を見せまいと必死である。
そして、京葉線のガード下を潜り、駅前ストレートも後半に差し掛かって来た頃――。
「…………ッ!」
何か異音が響いたと思った瞬間、S2000のボンネットから大量の白煙が吹き上げた。
――エンジンロック。その可能性が予測出来ないほど無知ではなかった筈なのに、咄嗟にクラッチを切って動力を絶てるほどに江は車を我が物には出来ていなかった。そして、それを極めて速度の乗った状態で引き起こしてしまったS2000は、完全にコントロールを失う。更に悪い事に、江はそれを車が今これだけの出力を得るようになるまで経験した事が無かった。ペダル操作は? ハンドルは――? 向きは全く定まらないのに、慣性の付いた車体は一向に止まろうとしない。加えて、公道ではコースを食み出すという事はクラッシュを意味する。一度左の側壁にヒットしたS2000は、車体を激しく損傷させながらも尚勢いを保ったまま、反対側に聳える中央分離帯へと突進する。そして再び壁に接触し、更に路上を舞った後、ようやくその動きを止めた。
「うわあああぁぁぁ――ッ! 江――ッ!」
慌てて車を飛び出して来た孝典の眼前に在ったのは、かつてそれがS2000の姿をしていたと分からないほどにフロント部を大破させた車の姿だった。急いでドライバーの下へ駆け寄ると、シートに凭れた江は、頭から血を流してぐったりしていた。
「おい江! しっかり! しっかりしろッ!」
懸命な孝典の叫びに、江はうっすらと目を開け虚ろな瞳を孝典の方へ向けた。
「ああ……歌野……。俺……どうなっちまったんだ……?」
何が起きたのか理解出来ていない様子の江に、孝典は言葉を返せなかった。
「なぁ、教えてくれよ……。俺は……何を求めていたんだ……? お前らの瞳に映っているものは何なんだ……?」
そこまで言うと、江は意識を失って頭を垂れた。友の事故を目の前にして、孝典はこうなる事を予想しつつも走る事を止めなかった自分を、ただ呪った。
江は重傷を負ったものの、命に別状はなかったが、S2000は再起不能なまでに破損していた。そして江が再び深夜の幕張へチューンドカーのハンドルを握って訪れる事はなかった。それまで当たり前のようにして走っていた幕張という場所に、怖れをなすようになってしまったのだった。
しかし、幕張の様相に変化はない。江が起こした事故は、単独とはいえかなり大規模なもので、普段であれば集う者達の間ですぐに噂されるほどのものである筈だった。だが、連日のように事故の繰り返されていた当時の幕張でそれは、事故を目の当たりにした孝典以外の者の記憶には殆ど留まらなかった。孝典にしても、江以外の事故も数多くあった筈だが、それを逐一覚えてはいない。それだけ、この時の幕張は混迷を極めていたのである。
『しかしながら、狂乱の宴はまだ始まったばかりだった。悪夢は、そう簡単に醒めはしなかった――。』
「環。このところ、以前にも増して幕張に行く事が多いけど、体とか大丈夫なの? 私は楽しいから良いけどさ。」
千歳の少々心配そうな言葉に、環は素気無く答えた。
「別に、どうって事ねぇよ。俺だって、楽しくてやってる事なんだ。最近、皆のレベルが上がって来てるからな。俺もしっかり走り込んどかねぇと、置いてけぼりを食らっちゃ堪んねぇだろ。バトルに事欠かないのは忙しなくもあるが、退屈するよりはマシって事さ。」
外面はいつも通りだが、今の状況を楽しんでいる様子を感じ取った千歳は、釣られて笑顔になる。
「良いなぁ。私も早くその中に混ざりたいよ。お金の目処は付いたから、後は手頃な車を見付けるだけなんだけどね。32Rも今となっては立派な旧車だから、なかなか良い車ってないんだよね。値段との兼ね合いもあるしさ。」
さも待ち遠しいといった様子の千歳。彼女の車探しも、いよいよ本格化しているのだった。
「その内に良いのが見付かるだろ。……その時は、先ずは俺と勝負だぜ。手加減しないで相手してやるからな。」
現在の幕張の状況を環が知らない筈もないのだが、彼の言動は危険な雰囲気を匂わせないし、一緒に居る千歳も、自分で走っていないからなのだろうか、やはりこの状況に鈍感な部分があるようだった。
そして今夜もR34スカイラインが幕張の地へと出撃して行く。混沌と化した深夜の幕張へ――。