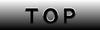― 20.往来〜Verkehr〜 ―
様々な想いを人は抱く。それは実に多岐に渡る。自身の事のみを考えた身勝手な想いもあれば、他人の事を思い遣る慈愛に満ちた想いもある。現実に即した冷徹にさえ映る想いもあれば、実現は到底不可能に思える理想の塊のような想いもある。幾多もの想いが人の脳裏を過ぎる。この地――幕張に集い来る者達も、各自が各日に異なる想いを持つ。数え切れない想いが、この地を行き交う。
元来、此処に集う者達の想いは同じ。そう、速さを追い求める事である。根底での心理が一致しているからこそ、深夜の幕張は特殊な空間足り得るのである。だが、そうなった理由――スピードに魅せられるに至った所以は、必ずしも同じではない。逆に考えれば、共通しているのは速さの追求のみ。それ以外の部分は、何ら一致していないとも云える。
だからこそ、時には想いの擦れ違いが起こる。自分の考えている事が、相手と合致しない。自分の思い通りにならない。同志の筈なのに、いや、同志だと思っているからこそ、その擦れ違いが許せない事もあろう。
それでも忘れるな。この地に群れる者達は、一つの意志の下に集められている。その事実は、否定しようがないのだと――。
『えーっ。まだ仕上がらないんですか?』
携帯電話の向こうで喋る敏行の声は、いかにも不満そうである。するとその相手の水看は、大きな溜め息を漏らす。
「軽く言ってくれるわね……。今回の作業は大掛かりだって言ったでしょう? それに……ちょっとこの所、私自身の体調も余り優れなくてね……。思うように仕事が進まないのよ。」
普段から余り快活な話し方をする方ではない水看だが、今日は普段にも増して元気がないようだった。
『え、そうだったんですか? ……済みません。そうとは知らずに……。でも、水看さんが体調を崩すなんて、珍しいですね。』
敏行は謝りながらも、正直な感想を述べた。確かに水看は連日休む事なく、徹夜に近いような状況で作業をする事も多く、体力的にはかなりタフなイメージがある。そんな水看だが、今の彼女が意気消沈しているのは、精神的な理由――皐月との一件を引き摺っている為なのであるが、水看自身も話す気がないので、敏行がそれを知る筈もない。それでも、敏行の発言に苛立ちを覚えてしまう。
「……私だって、人間の体と想いを持っているのよ。いつでも万全の状態を保てるわけじゃないわ。」
感情は声質にも表れる。それを受けて敏行は、自分の発言が水看の癇に障った事に気付いたようだった。
『……済みません。』
ゆっくりと、しかししっかりとした敏行の謝罪の言葉に、水看は感情を顕にし過ぎたかと少し悔いたが、今はその事を直接詫びる気にはなれなかった。
「……兎に角、悪いけどもう暫くは掛かるから。大人しく待っときなさいね。」
そう言って電話を切ると、水看は再び溜め息を吐いた。
「……御免なさいね。敏……。あんたが悪いわけじゃない。私が勝手に自分の過去を重ねてるだけで、あんたに当たるのは筋違いなのにね……。」
自分は幕張へ逃げて来たつもりだった。忌まわしき過去と決別する為に。ところが、現実はそれを許してはくれなかった。まるで追い掛けて来るかのように、幕張での事象は悉く水看の過去へと繋がって行く。
「私は……一体何処へ向かっているのかしらね……。過去から逃れられないのはある程度は致し方ないとしても、これはちょっと度が過ぎるんじゃない……?」
誰に向かって言うわけでもなく尋ね、それから皮肉な表情で弱々しく笑った。とはいえ、考え込んでも気分が晴れる訳でもない。――取り敢えずは目の前の業務を片付けるのが先決であろう。
「野呂。アンタら、ご飯済ませちゃえば? 私が代わるから、先に食べときなさいよ。」
水看は事務所から出て来ると、作業中だった二人に声を掛ける。基本的に昼間の現場は二人に任せ、事務やC/Pセッティングなどインドアな作業をメインで行う水看だが、エンジン組み上げ等の重作業は自ら行う。
「あ、済んません。じゃあ、ちょっと行ってきます。真空引き終わったらガス入れて終わりですから。」
「ガスは134? 分かったわ。そっちは?」
「こっちは型取り終わったところですね。あとは延々と鉄板曲げるだけですかね。」
「了解了解。」
事務所に消えて行く二人を見送り、水看は作業に取り掛かった。エアコンの方はまだ時間が掛かりそうだ。二柱リフトに揚げられている方の車両に歩み寄ると、側には無造作に置かれた型取り用の方眼紙があった。手に取り、工場の一角に設けられた工作室へと向かう。
国道を行き交う車の数が多くなって来た。街が眠りに付くまであと数時間。街がもうひとつの活動の場となるまで数時間――。
街を行き交う人はまだ絶えない、夕暮れ時のTanz mit Wolkenにて、今日は敏行と美由、尊が顔を揃えていた。そこで話の成り行きから敏行は水看にインプレッサの作業の進行具合を訊こうと思い立ち、そして先のやり取りがなされたのであった。
「敏さん、何だか機嫌悪くないですか……?」
傍で電話する様子を見ていた尊が、話し終えて携帯電話を置いた敏行に向かって、遠慮がちにそう言った。すると敏行は、一息吐いてから席に座った。
「そうかな? まぁ、僕もちょっと無神経だったのかもね。水看さん、今あんまり元気ないみたいだったよ。」
言いながら笑って見せたが、実際に気分が晴れやかではないからなのか、或いは水看に言われた事で気落ちしているからなのか、その表情からは余り元気さを伺う事は出来ない。
「でも、二回も謝ってたじゃん。何か水看さんを怒らすような事言ったんでしょ?」
しかしながら同じくその場に居た美由も、具体的な指摘をする。
「拙い事言ったつもりはなかったんだけどな。水看さんも、虫の居所が悪かったのかもしれないね。」
あくまで自分の機嫌の悪さは否定する敏行だが、美由も食い下がった。
「敏ちゃんの方もあんまり良い所に虫が居るとは思えないけどねぇ。尊がそう感じたのも、分かる気がするよ。」
美由は特に深い意図があって追求したわけではなかったのだが、詰られた敏行はややムッとした。
「何だよー。そんなあからさまに不機嫌な態度を取ってたわけでもないだろ。そりゃ、早くインプレッサが仕上がんないかなってのはあるけどさ……。それに、その意味じゃ、美由だって偉そうな事言えたもんじゃないじゃないか。」
切り返した敏行にも、それ程強い反感があったわけではないのかもしれないが、言われた美由もまた剥れる。
「一言多いよぉ。私に矛先向けなくたって良いじゃん。気にはしてるんだからさぁ……。」
その様子に敏行は言葉を窮してしまい、場には重い雰囲気が流れる。挟まれた尊はどうしたら良いかとオタオタしていたが、やがて来た楓が空気を一気に変えてしまう。
「はいはーい。二人共喧嘩しないで、仲良くしましょうね。ご飯出来たわよ。お待たせ〜。」
相変わらずの調子で現れた楓の前に、美由は渋々ながらも向き直って機嫌を直した。一方の敏行は、慣れてしまって普段は意識しないが、美由の母親の居る場での事だったと気付かされ、少々気まずさを感じる。尤も、楓の方は何ら気にしていないようだが。
「今日は新メニューの試作品よ。皆の反応で採用するかどうかを決めるから、篤と毒見してね。」
「おばさんがさらっと毒見とか言うと、却って不安になりますね……。」
そう言いつつも、尊は場の雰囲気を楓が和ませてくれた事で、嬉しそうにしていた。実際、敏行も美由も先までと比べれば大分と明るくなっている。ただやって来ただけでこれほどの影響を与えられる楓も、大したものである。
「うん、美味しいと思います。ただ……何だか見た目のイメージとは随分違う味ですけど。」
「その意外性が面白くない?」
「うーん、どうだろう。あんま食べ物の外見に意外性があっても……。」
各自が毒見を兼ねた夕食に、思い思いの意見を述べて行った。
やがて試食会は終わり、食後のコーヒーを味わっていた際に、階下で後片付けをしていた悠一が美由を呼び出した。
「おーい、美由。ちょっと手伝ってくれ。」
「え〜。食後の憩いの一時なのに〜。親が死んでも食休みって云うじゃん。」
美由の反論も、悠一には聞き入れられない。
「敏や尊に手伝わすわけにもいかんだろう。そんな掛からんから、早く来い。」
そう言われて美由は仕方なく席を立ち、さも嫌々といった素振りで階段を降りて行った。それと入れ違うようにして、楓が二階の客席へと再び姿を現し、そして空いた美由の席に着いた。
「さて、美由の代わりに私が休憩させてもらおうかしらね。」
「え? その為に美由が呼び出されたんですか?」
尊が訊くと、楓は明るく笑いながら身振りでそれを否定する。
「あら、そういうわけじゃないのよ? 私の方は一段落したところで美由が呼ばれたから、丁度良いかなと思ってね。」
言いつつ持っていたお盆をテーブルの上に置く。それからややあって、楓が話を切り出した。
「さっきは美由がご免なさいね。あんな事言ってる美由こそ、虫の居所が悪いってものなのにねぇ。」
謝られた敏行は、とんでもないといった様子で両手を振る。
「いやいや、そんな! 僕の方こそ突っ掛かるような態度取っちゃって、悪かったと思いますよ……。」
聞かれていただけでも肩身の狭い思いなのに、楓の方から許しを求められては、敏行としても非常に心苦しかった。対する楓は慌てる敏行を見て可笑しそうに笑ってから、少し真顔に戻って口を開いた。
「……美由もそうだけど、最近何となく皆焦ってない?」
穏やかに発されたその言葉に、敏行も尊もハッとした。
「貴方達の事だから、やっぱり車に関係した事なんでしょうけどね……。皆の中で大切な事だから、それの良し悪しが日常のちょっとした仕草にも表れる事ってあるじゃない。」
話を聞く二人の表情は、神妙なものとなっていた。
「……やっぱり分かるものですか?」
尊の質問に、楓は頷きながら答える。
「美由は私の子だから勿論の事、敏君や尊ちゃんもよくウチに来てくれて顔を合わす事も多いから、様子が違うと何となく感付くじゃない。皆、元々一生懸命になれる性格だけど、その在り方は以前よりもちょっと変わって来てるように思うのよね。最初の頃は兎に角楽しんでるっていうイメージだったけど、今はそれだけじゃない。そうね……鬼気迫るとまでは言わないけど、迫力みたいなものを感じるのよ。正しく、何かに追い立てられるかの如くに。それが何故なのか、私には勿論解らないんだけどね。」
それに対して二人は言葉を返す事はしなかったが、すっかり聞き入っているようだった。
しかしその姿を確認した楓は、打って変わっていつものような明るい声で言う。
「なーんてね。そんな事を、歌野君が言ってたのよ。それをちょっと格好付けて、受け売りさせてもらったってわけ。」
それを聞いた敏行達の緊張の糸は、途端にぷっつりと切れた。
「う、受け売りだったんですか?」
すっかり愕然とした敏行には、そう訊くのが精一杯だった。尊の方も何とも言えないといった様子で苦笑いを浮かべていた。
「何にせよ一生懸命になるのは良い事だけど、過度に熱くなり過ぎちゃ駄目だって事なんじゃない? 歌野君も良い事言うわよねぇ。」
楓らしい飄々とした様子でそれだけ言うと、お盆だけを持って席を立ち、パタパタと階下へ去って行った。残された敏行と尊は暫く苦笑したままで居たが、やがて敏行がふと言った。
「……あれ、本当に歌野の受け売りなのかなぁ。」
すると尊はやや表情を落ち着けてから答えた。
「どうでしょうね……。何たって、おばさんの言う事ですからね……。」
その言葉の意味は、楓の発言が当てにならないという事ではなく、寧ろその逆である。ただ、敏行の言う通りそれが実際に孝典の言葉を真似ただけのものなのかどうかは量りかねるというだけの事だった。そんな楓の言葉を思い返しつつ、尊はゆっくりとコーヒーを啜った。
「どちらにせよ、私は確かに焦っているのだと思います。GT-Rに乗り換えたのは、パワー不足への焦燥に他ならないですからね……。」
対する敏行も、考え込むように少し俯きながら言葉を続けた。
「僕は……僕も同じなんだろうな。他者とのレベルの差を痛感させられて、せめてマシンの性能は高くして備えをしておこうとする……。そこに焦りがないとは云えないよな……。」
窓の外はいつしかすっかり日が暮れ、新都心は夜の闇に包まれようとしていた。
東京都の都心からやや外れた場所に位置する、広大な敷地を構えるファクトリー。その世界では言わずと知れた大手チューニングショップBeyond Limitでは、今日も沢山の車が各工員達の手で扱われている。それは夜になっても変わらず、絶対数こそ減っているものの、工場の灯かりが消える事はない。
その中でも一際異彩を放つ二台の車が在った。極めてハイレベルなチューンの施されている、銀色に輝く二台の車もまた、このショップで手掛けられているものである。そんな車の持ち主である博文と澄香と共に話をしているのは、Beyond Limitの社長、椎名柾臣であった。
「相変わらず二人揃っての登場だが、これくらいの時間に来るのは珍しいな。仕事が早く上がれたのか?」
夜とは云ってもまだ更けてはいない時間帯に訪れた二人に対して、柾臣が尋ねた。
「いつも残業じゃ、適いませんよ。そんな仕事人間になりたくはないですからね。」
自分の事なのに呆れたようにして言う澄香の様子からは、普段の忙しさが窺える。
「全く、日本人ってのは働き過ぎなんだよ。尤も、俺も時間的には働きまくってる方だろうが……業種的には、ちょっと訳が違うしな。」
そんな調子で雑談を交わした後、澄香が言った。
「そういえば、少し前になりますけどね。幕張で水看さんのショップのステッカー貼った車と会いましたよ。」
対する柾臣は、一瞬少し驚いたようだったが、すぐに落ち着いた表情に戻って答えた。
「成る程……。幕張を走ってりゃ、出遭って当然か。ステッカーを貼ってるとなると……ロードスターの方か。速かったろ? REに積み換えてるし、乗り手の方もなかなかのもんだと聞くしな。」
水看からある程度は近況の説明を受けているので、柾臣も美由や彼女の愛機ロードスターの事は、情報としてのみであるが知っていた。
「ええ。噂に違わず、と云ったところでしたね。……時に、ロードスターの『方』と言ってましたけど、他にも幕張の車の中で、水看さんの手によるものが在るんですか?」
同意に続けて疑問をぶつける澄香。
「おっと……。流石と云うべきか、鋭く突っ込んでくるな。……その通り、もう一台居るんだよ。そっちは、ステッカー貼ってないらしいから、見た目にゃ判断出来んがな。車種は……インプレッサワゴンだ。」
インプレッサワゴン――その言葉を聞いて、尋ねた澄香も、そして隣の博文も驚く。
「……そうですか。あいつのインプレッサも、水看さんが手掛けているものとは……ね。」
言いながら博文は軽く口元に笑みを浮かべた。
「ほぅ。お前の方も曰く有り気な言い回しをするじゃないか。……インプレッサワゴンも知ってるんだな?」
「そりゃあもう。……幕張に行って、最初に出遭ったのがあいつですから。浅からぬ因縁……。忘れられる筈がないですよ。」
あくまでクールさを装いながらも、何処か嬉しそうにする博文。それを横目に、澄香が柾臣に再び気に掛かった事を問い尋ねる。
「私達がここでお世話になり始めたときはもう水看さんは居ませんでしたけど、彼らの車はその頃から水看さんが作っていたんですか?」
「いや、インプレッサやロードスターを見るようになったのは、まだ此処半年くらいの事だったと思うがな。今もあいつの店は、表立ってはドレスアップとかライトチューンだとかをメインに扱ってるって事になってるし。」
澄香が質問した意図は、博文にもすぐに解った。彼らがS201に乗って幕張に赴き、インプレッサワゴンと出遭ったのは凡そ1年前。その段階では、まだ水看によって手は加えられていなかった。よって、恐らくは現在よりもチューニングのレベルも低かったと考えられる。
その為に敏行との出遭いの意味が薄れるわけではない。寧ろ、それにも拘らずあれだけの走りが出来たのか――。二人は言葉にこそしなかったが、心中でそんな事を思っていた。
「博文さんに澄香さん。ちょっと久し振りだよね。」
そこへ不意に別の声が聞こえて来た。声がした方を向くと、そこには柾臣の娘、皐月が立っていた。
「ああ。皐月か。そんな久し振りか? そういや、少し前に来た時は留守にしてたな。」
博文の言葉に、皐月は少し複雑そうな表情をしつつ答えた。
「うん、ちょっとね……。ねぇ、澄香さん。ちょっと話があるから、裏手に行こうよ。此処じゃ騒がしくてゆっくり話も出来ないしさ。」
わざわざ場所を移そうとする皐月に、柾臣が苦笑しながら言う。
「何だよ。俺の居る前じゃ話せない事でもあるってのか?」
すると皐月は、戯けたようにして言葉を返した。
「女の子同士の秘密のお話があるの。お父さん、立ち聞きなんてしないでよ? あ、でも、博文さんは来て良いからね。」
「おい、女の子同士の話じゃなかったのか。」
更なる苦情の申し立てを、皐月は努めて明るく却下する。
「博文さんは良いの。さ、二人とも、行こ。」
そう言って二人の手を引き、その場から連れ去って行った。
「……俺は女扱いなのか?」
途中で博文はぼそりと呟いた。
一方、娘に取り残された柾臣は、その事への苛立ちを近くに居た工員にぶつける。
「オイそこ! いつまで煙草吸ってんだ!! 休憩終わり!!」
「社長。それ、八つ当たり………。」
唐突に怒鳴られた工員は不満気に言ったが、柾臣は半ば自棄にそれを一蹴する。
「五月蝿ぇ!!」
小さい頃は父さん子だったんだがな――。今に始まったわけではない反応だと云うのに、柾臣は寂しげな表情を浮かべていた。
工場の裏に広がる敷地もまた広大であるが、時間も遅く一般の客の出入りもないので、表に比べれば閑静と云えよう。
「大切な話でもあるんだけど、お父さんには席を外してもらってた方が話し易い内容でもあるんだ。丁度さっき皆が話してた、姐さんの事なんだけどさ……。実は、前にボクが留守にしてたのは、姐さんの所へ行ってたからなんだ。」
場所を変えた事に加えて、皐月の話し方も、彼女の話そうとする事柄の重さを漂わせる。
「皐月は水看さんと仲良いみたいだもんね。でも……どうしてそれを私達に?」
最近は澄香達も水看の名を聞く機会が増えていたが、実際に面識があるわけではないので、水看に関する話を積極的に聞かされる立場にはないと、澄香は感じた。しかしながら――。
「さっきお父さんがしてた話からも、勘の良い二人なら気付き始めてるかもしれないけど、間接的だけど二人は姐さんと大きな繋がりがあるんだ。それは二人だけじゃなくて、姐さんも知らなかった事なんだけど、こないだ行った時に話したんだ。だから……二人にも知っておいてもらうべきなんじゃないかと思って。」
そして皐月はゆっくりと話し始めた。S201が水看の手によって作られた事から、それを巡る出来事における水看の想いまで。水看も、敏行も、そして博文と澄香も幕張を介して強い結び付きを持っているのだという事を、皐月は語った。
その事を知った博文と澄香は、暫し感慨に耽るかのようにして黙りこくっていたが、やがて博文が口を開いた。
「大方の内容は解した。まさかそこまでの事とは……本当に予想だにしなかったな。」
続いて澄香も言う。
「良いじゃない。こんな事、そうそうないわよ。……ま、こんな物言いは水看さんには申し訳ないのかもしれないけどね。」
澄香の言葉尻からも、二人がこの繋がりに高揚感を抱いている事が分かる。だが、その後で博文が途端に厳しい顔付きで皐月に問い尋ねた。
「だが……お前は俺達にそんな話をして、どうしたかったんだ?」
突然の言葉に、皐月はびっくりして博文の方を向いた。
「水看さんの相関の中に俺達が含まれていて、それ故にお前がその事を俺達に話そうとした気持ちは解らないわけじゃない。でもな……。俺は事情を知ったところで、何も出来ないぜ。お前や水看さんの気持ちを救えはしない。話を聞く以前と同じように、幕張の地を走り続けるだけだ。それが、皐月達の苦悩を深める事になったとしても……な。」
言われた皐月は応対に困っていたが、そこへ澄香が口を挟む。
「まぁまぁ、あんたもそんな言い方して皐月を困らせないの。……とはいえ、生憎私もこいつの意見に反対ってわけじゃないんだけどね。私達も……もうすっかり幕張という場所に心を奪われている。走るなと言われても、それは無理な相談なのよ。だから……貴方の話を聞いてあげる以上の事は出来ないのが実情なのよ。……ごめんね。」
博文とは違って穏当に話す澄香だが、その言葉からは博文と同様の確固たる意志が見受けられる。皐月はそれをすぐさま素直に受け入れられるとは思えなかったが、二人の想いには観念したという様子だった。
「……姐さんも何で幕張なんかに店を構えちゃったんだろうね。司さんがS201で向かったのも幕張だったって事は、姐さんだって知ってたのに……。でも、仕方ないのかな。首都高で名立たるシルバーブレイドの二人や、姐さんですら惹き付けられるんだから。魔力とも思しき何かが、幕張という場所にはあるんだね……。」
愁えた表情を織り交ぜながら、皐月は静かに言った。
「……皐月だって、自身の車を駆ってその地を訪れれば、自ずと分かる事だ。伝聞で知れる事には限界があるからな。」
博文の言葉に対して、皐月はやや無理に笑顔を浮かべながら答えた。
「ボクは暫くは良いかな。色んな事の根源の地だからって事もあるけど、幕張の持つ魔力は魅力的であると同時に、ボクにとっては恐怖でもあるからね。まだボクは、その渦中に身を置くだけの覚悟がないんだ……。」
皐月自身も幕張という場所に興味がないわけでは決してないが、それ以上に水看に纏わる因縁から何処か抵抗のようなものも感じてしまっている。彼女が幕張へ行きたがらないのは、どうして回りの人間がそこまで幕張に拘るのか、理解しかねる部分もあるからだった。
そんな心情を察したわけではないのだろうが、皐月の気持ちに向けたかのような言葉を、博文は述べた。
「……そう感じるのなら、無理には勧められないがな。ただ、幕張という地そのものが元から強い魔力を持っていたと考えて怖れているのなら、それは少々思い違いかもしれないぜ。同じ想いを持つ者が互いに呼び合い、自然発生的に生み出された結果が今の幕張であるに過ぎない。それが幕張という地理的な場所である必然性はなかっただろう。……そんな考え方も出来るんじゃないか? だから、もし俺達が走っているという事を理解出来ないのでないなら、お前も幕張に見合う人間と思って、問題はないと思うがな。」
それに続いて澄香がやや明るい調子で口を開くのを、皐月は更に黙って聞いていた。
「博文が言うと、何だか脅迫染みて聞こえるのよねぇ。私らなんて、首都高を走る片手間で、たまに幕張を走ってるだけだから、偉そうな事言える立場じゃないのにね。幕張に相応しいかどうかを選ぶのは、私達じゃない。そもそも私達だって、本当に選ばれているのかどうかは判らない。ただ自分でそう在りたいと勝手に願っているだけなのかもしれないのよ。」
やはり澄香の方が博文よりも一歩引いたかのような意見を述べるのだが、言わんとする事は二人とも同じであるように、皐月には感じられる。
「……澄香さんはともかく、博文さんまでもがそんなに思いを懸けるなんて、珍しいよね。ボクには、まだ解らない……。でも……姐さんも二人みたいに、前向きに幕張の地と向き合う事が出来るようになれば良いのにね。積み重ねて来た悲しみは深いから、そう簡単には行かないんだろうけど、きっと姐さんも本当はあの場所にそぐわない人間なんかじゃない筈だから、いつかはそんな日を迎える事も出来るんじゃないかな……。」
未だに物憂げな様子を残しつつも、少しだけ晴れやかさを皐月は取り戻していた。
「……さぁて、二人とも! 缶コーヒーも出したし、乙女なボクの秘密の話も聞けたし。オイルくらい換えてってよね!」
そして次に言葉を発し終えた後には、満面の笑みを浮かべていた。尤も、そこにはかなりの含みがあるが。
「……え。だって俺ら先週エンジンオイル換えたばっかりじゃ……。」
「ミッションで良いじゃん。」
「いや……。あれもまだ確か8000kmくらい走れるし……。」
「そうねぇ……。ま、お礼代わりに換えてくか。暖まってからがちょっと入り渋いのよね。いつものより一段固めにしといて。」
突然な皐月の無茶振りに狼狽える博文だったが、受け流す澄香の言葉に、彼もしょうがないとばかり頭を振る。
「全く……。じゃあ、俺はいつも通りの頼むわ……。下回り、キッチリ洗えよな!」
「毎度ありー♪」
そう言うと皐月は博文の180SXに向かってパタパタと掛けていく。800ps対応のツインプレートを手慣れた様子で移動させる皐月を見ながら、二人は何となく安心した。
――彼女にもいずれ、あの場所で会う事になるだろう、と。