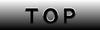― 19.回顧〜Rückblick〜 ―
過去を振り返るって行為をどう思う? そんなものに囚われず、真っ直ぐ未来へ向かって歩んで行くべきか? それも一理あるよな。時の流れは一方通行。過ぎ去った昔日は不可逆。幾ら恋い慕ったところで、戻るなんてのは叶わぬ夢だ。
けどな。過去の上に現在が成り立っているのも事実だ。過去がなければ、現在もそして未来もない。過去の存在は否定しようがない。だから、それを全く無視して進むというのも無理があるんじゃないのか?
人は――少なくとも俺は、脇目も振らずに一心に未来を見詰める事が出来るほど強い人間じゃない。過去を懐かしく想ってしまう事も間々ある。だから……いつもとは云わないからさ。たまには、古の幻影に想いを馳せさせてくれよ。
……ああ。ついでだから、そんな俺の想い出話に少し付き合ってくれると嬉しいかな。つまんない話になるかもしれないけどさ――。
頻闇に包まれた幕張新都心には、今日もエキゾーストノートが響く。それ自体は普段と変わらぬ光景だが、集う者達の様子はそうではなかった。何処となく騒めき立っており、そして道端には次第に人集りが出来始めている。日頃は無駄な面倒を避ける為にも、過度にギャラリーが集中して騒ぎ立てないようにすると云うのが、暗黙の了解とされている感のあるこの場所なのだが、今走っている面子を見れば、それが破られてしまうのも致し方ないと云える。純白のNA1 NSX、萌黄色のSA22C RX-7、深緑のZ15 GTO、そして赤みがかったシルバーのR34スカイライン。現在の幕張でトップを張るこれらの車が、一堂に会して走っているのだ。四台が本気の鬩ぎ合いを見せているのかどうかは分からないが、彼らの走りが纏めて見られるというだけでも、充分に一見の価値があると云えるのである。
四台は見浜園の交差点に差し掛かっていた。先ず、NSXが先頭でコーナーへ飛び込み、それにRX−7が続こうとする。ところが、GTOがインから強引にRX−7の懐に差し込み、動きを封じる。RX−7は無理に競らずに素直にGTOにインを明け渡し、そこからGTOは前へと出て行く。二台の交錯からやや遅れて、最後にスカイラインが交差点へ進入する。
「うおっとッ!」
RX−7を駆る歌野孝典が声を上げる。GTOの割り込みにより、やや苦しいラインでのコーナリングを余儀なくされた孝典は、立ち上がりで軽いホイルスピンを起こしてしまったのだ。とはいえ、大事に至る事はなく、すぐにGTOの後を追う。
「ったく……。毎度ながら、危なっかしい事ばっかするな。あいつは……。」
苦笑しながら、前方を走る車に対して文句を述べる孝典。GTOのドライバー、関口陶冶は、例え軽く流している時であっても、並走している車があれば積極的に仕掛けて来る人間である。特にこの四人で走る時は、前に後ろに忙しなくポジションを移動しながら、事ある毎に他の車へと絡んで来る。
「傍から見ればバトルを盛り上げるエンターテイナーとも云えるが……仕掛けられるこっちは冷や汗もんだよ。」
とは云え、陶冶はあくまでもエンターテイナーである。悪辣な、或いは危険な仕掛け方はしない。彼が攻めて来るのは、必ずそれが可能なだけの相手との間合いがある場合のみであり、そういった状況を好んで作り出そうとしているだけなのである。つまりそれは、相手の車の動きの読みが抜群であるという事をも表している。
そんな二台のやり取りを尻目に先頭を走るNSXを操るのは藤井沙和。極めて冷静沈着な走りをするタイプで、陶冶とは対極に位置するとも云える。前を走る時は後ろからの揺さ振りにも全く動じる事はなく、後ろを走る時も好機が訪れるまでじっくり待つ事が殆どである。その代わり、訪れた好機は絶対に逃さない。相手の僅かな隙を突いて、瞬時に抜き去るのである。その為、実戦では四台の中でも頭一つ抜け出した実力を持っている。
そして、最後尾に食らい付いているスカイラインの乗り手の名は支倉環。四人の中でも最年少の彼の走りはやや荒削りな部分があり、幕張のトップに数えられているとはいえ、他の三人に比べると少々精彩を欠くのも事実である。しかしながら、人一倍向上心があり努力家の支倉は、時に驚くべき底力を発揮する事もあり、やはり侮れない存在である。
この四人は時に幕張四天王と呼ばれ、この場所の頂点に立つ走り屋として恐れられていると同時に走り仲間でもあり、よくこうして連れ立って走っていた。
尤も、今では有名になり過ぎてしまい、昔ほど気軽に四人が纏まって走る事は難しくなってしまった。それでも今日のように皆で走りたいと思う事もあるのだが、走り終わった後は一旦バラバラに幕張を後にし、ある程度離れた場所で再び集まるという形を取っている。今日は千葉港の奥地での集合となっていた。
「あーあ……。 まーた俺が最下位かよ……。」
舌打ちしながら、さもかったるそうに車を降りる環。
「くっくっく。ビリッ穴がすっかりお前の定位置になってしもうたな。走り始めの頃の方が、今よりも速かったんとちゃうか?」
厭味たっぷりの陶冶の言葉に、環は悪態を吐きながら切り返した。
「五月蝿ぇなぁ……。オメェだって似たようなモンじゃん。 陶冶が沙和のアタマ取ったとこだって、見た事無くねぇ?」
「喧しわ! 俺の後ろを走っとる癖に、偉そうな口抜かすな! それに、せやったら歌野にも言うたれや。」
振られた孝典は苦笑しながら口を開く。
「当て付けるなよ。俺は案外先頭に立ってる事も多いと思うがな。なぁ、藤井?」
そう訊かれた沙和は、あしらうように笑みを浮かべながら答えた。
「さぁ、どうだろうな。」
「かー……。こーゆー時の沙和、ムカつくわー……。」
環がぼそっとそう言うと、沙和の冷静な表情の中にもやや拙かったかという思いが滲んだ。
「いや、別にそういうつもりではなかったのだがな……。支倉だって、時に異様な冴えを見せる事があるではないか。あの時の支倉は、私とてとても追えたものではないぞ。」
褒められた環は少し得意げになった様子に幼さを垣間見て笑った孝典が、ふと沙和に尋ねた。
「そういや藤井。変えたタイヤの調子はどうだ?」
走る前に孝典は沙和からNSXのタイヤの銘柄を変更した事を聞いていたので、それが気になっていたのだった。
「そうだな……。前のBSの時の方が絶対的なグリップ力は強かっただろうな。今のヨコハマの方が良くも悪くもしなやかというか、バランスは良いのかもしれんが、攻めた時にはちょっと弱さを感じる部分もあった。……まぁ、今日一回のみでそこまで正確に性能を把握出来るものでもないがな。アライメントも幾つか試してみた方が良いだろうしな。」
沙和の述べる感想を成る程と頷きながら聞いていた孝典だが、そこで環が口を挟んだ。
「そうかぁ? 俺は別にヨコハマも嫌いじゃねぇぜ?」
自身は現在ヨコハマのタイヤを使用しているわけではないが、嘗ての経験からそう述べた。そしてそれに陶冶が満足そうにして言葉を足す。
「せやろ? おう、千歳! お前もタイヤはヨコハマにしとけ! ネオバや。ネオバがええねん!」
話を振られた千歳は、苦笑しながら答えた。
「私、車持ってないよぉ。」
「だから、車買うたらの話や! 何なら、俺みたくA048とかもありやで? Sタイヤ万歳ってな!」
話を押し進める陶冶に対して、千歳は益々苦笑いを浮かべたが、とはいえ、それは真に対応に困っていたというわけではなく、その笑みは紛れもなくこの状況を楽しんで浮かべたものだった。
知らぬ人間が見れば、千歳は蚊帳の外で放ったらかしにされているようにも映るかもしれない。だが、千歳はこうして四人が楽しそうにする様を見るのが好きだった。そして四人の側もそれを知っているからこそ、千歳に対して過度に気を遣う事もなかった。孝典が話題を戻す。
「ま、銘柄はともかくとしても、タイヤチョイスは重要だよな。タイヤってのは、車の部品の中で唯一地面と接している部分であり、それ故に最終的にはエンジンが稼ぎ出すパワーの全てはタイヤを通して路面に伝えられるわけだ。手軽に交換出来る部分とはいえ、その重要度はかなりのものだと思うな。」
真面目に語る孝典の言葉に、陶冶は例の如く不敵な笑みを浮かべながら続く。
「くっくっく。確かにな。その意味では、チューンドカーってのは恐ろしいもんやでな。エンジンパワーはノーマルの数倍に達しているにも拘らず、タイヤの設置面積の方はインチアップしたところでせいぜい二倍にも満たない程度や。単純計算からすれば、それは余りにもアンバランス過ぎる……。そう考えると、時にビビリが入ってまう事もあるわな。」
その時、一瞬吹いた強風による木々のざわめきがやけに不気味に聞こえて、孝典は人知れず身震いした。
「ん? どうした?」
孝典の異変に気付いて掛けて来た沙和の声にハッとして他の人間を見回すが、えも言われぬ瞬間的な恐怖を感じたのは、自分一人のようだった。孝典はそんな自分を臆病だと情けなく思いながら、笑って何でもないと取り繕った。
この四人は――正確には五人だが、千歳自身はまだ車を持っておらず、環の助手席が彼女の指定席だった――ただ単に同じ時間に同じ場所を訪れる人間だというだけでなく、本当に仲の良い間柄である。実際、深夜の幕張以外の場所でも顔を合わす機会を作る事もある。勿論、それは彼らが互いに気が合うからでもあるのだが、幕張に集う走り屋全体がそういうムードを持ってもいた。車自体はかなりチューンの進められたものも多く、云わば真面目に走りに取り組んでいる者達が殆どである。しかしながら、人間同士の関係のおいてはどちらかと云うと和気藹々とした、和やかな雰囲気が先行していた。元より、あくまでも「走り屋の集う場所にしては」と云う前置きが付くが。
日が暮れたばかりの街並みは、まだまだ人の行き交いも多く、賑わいを見せている。文明の利器は街中を明々と照らし、空が闇に包まれている事を忘れさせる。雑多とも云える人波の中には、環と千歳の姿も在った。
「久し振りだね。二人でお酒なんて。」
決して口数が多い方ではない千歳だが、優しい口調の端々に何処か浮ついた感じがする。 環は機嫌の好い時の彼女のその話し方が好きだった。
「まぁ居酒屋みたいな所だけど…。飲むと運転出来ないから、なかなか来ねぇよね。」
当たり前の事だが、彼らにとって見れば割とシビアな選択である。こうして飲みに行くのも良いが、車で深夜の街へ繰り出すのは尚良い。そんな二人からすれば、飲みに行く機会の方が少なくなってしまうのは、必然とも云える。
「付き合い始めの頃はよくご飯食べたり飲みに行ったりしたけど、最近は専ら幕張へ走りに行ってばっかりだものね。環も幕張へ行くのがすっかり当たり前になっちゃったし。」
千歳は別に苦言を呈しているわけではなく、事実を指摘したに過ぎない。
「私は楽しいから、別に嫌な訳じゃないけど。」
「まぁな……。俺も結構嵌ったって事じゃね?」
言葉は少ないが、環もそれを自認している。
「やっぱり、あの時が切っ掛けになったのよね。」
「あの時」か――。環がそう言おうとした瞬間、後方から大きな呼び声が聞こえた。
「お〜い! 環に千歳やないかい! 奇遇やなぁ!」
それを耳にした瞬間、環は嫌な予感がした。声の主が誰であるのかは明白である。そして、この状況で彼と出会ったとなれば――。
「なんや、お前ら。これから飯でも食いに行くんか?」
関西弁を喋る大柄な男を前にして、千歳は素直に問いに答える。
「うん。これから二人で飲みに行くのよ。」
「ばッ……!」
環が慌てて止めようとしたが、時既に遅し。
「お、それやったら、俺も連れてけや! 人数は多い方が楽しいやろ?」
完璧に予想した通りだった――。環は一人頭を抱えつつも、せめての抵抗を見せる。
「あぁ全く手前はいっつも何でそう気遣いっつぅのがねぇのかねぇ。 恋人同士が二人で居るってのによ……。」
真剣に嫌そうな顔付きの環の様子など意に介さず、陶冶は無闇に楽しそうに環の肩をバンバンと叩いた。
「ええやないか、ええやないか! そんな気遣い、俺に期待するだけ無駄ってもんや。」
品なく笑う陶冶に肩を掴まれて、環はいよいよ渋い表情をした。
「……ったくよ……。」
一方の千歳は特に文句を言う事もなく、二人の様子を面白そうに眺めていた。
「良いじゃない。環。陶冶君なら、今更気を遣って場が悪くなる事もないでしょ。」
「おッ! 流石は千歳! 環と違うて、話が分かるな!」
陶冶が水を得た魚の如く、得意気な表情を浮かべる。そんな陶冶に肩を掴まれたままの環は、そっぽを向きながら静かに笑った。
庶民的な雰囲気の漂う居酒屋には、既に大勢の先客が居たが、環達は三人と云う少人数であった事も手伝って、待たずに席に着く事が出来た。
「せやなぁ。先ずは生中三つやろ。それから、刺身盛り合わせと、串はつくねと皮を六本ずつ。後は……。」
お通しを持って来た店員に、陶冶が慣れた様子で注文を入れており、環と千歳もそれに任せている。環が嫌な顔をしたりはしたものの、基本的にこの三人は仲が良い。こうして三人が揃うのも、それほど珍しい事ではなかった。
「週半ばだってのに、混んでやがんなぁ……。」
もう少し空いている事を期待していた環は、周りの喧騒をやや憎らしげに見渡した。
「しゃあないやろ。俺らかて、その中の一部なんやから。」
対する陶冶は然して気にする様子もなく、ビールがやって来るのを心待ちにしていた。
「にしても、陶冶君は何か予定があったんじゃないの?」
お絞りで手を拭きながら、千歳は陶冶に尋ねた。
「別にそういうわけやない。今日は仕事が早うに終わったから、街をぶらついとったら、お前らにばったりっちゅうわけや。いやぁ、出歩いてみるもんやな。」
答える陶冶は実に嬉しそうである。
「飲んでない内からそんなに騒ぎやがって。後々が思い遣られるぜ……。」
環が皮肉めいた口調で言ったが、その顔付きは先のように嫌そうなものではない。環も満更でもないのだろう。やがてやって来たビールを皮切りに、三人は周囲の喧騒に負けない盛り上がりを見せて行くのだった。
「くっくっく。お前、ええ度胸やないか! 俺にそんな口叩くとはな!」
「うっせぇなぁ……。何様のつもりだよ。俺が年下だからって、いつも見下しやがってよ!」
「年下なのは事実やろ。それは永遠に変わる事はない。年上の人間にはな。敬意を持って接するもんやで。」
「手前が敬意を得られるような人間とは思えないがね。」
騒ぐ二人は傍から見れ酔っ払って喧嘩を始めたかのようにも見えるが、実際にはそういうわけではない。彼らが飲みにくれば決まって一度は起こる事態であり、彼ら自身も別に本気で揉めているわけではない。蚊帳の外の千歳も、何処か楽しそうに二人の不毛な論戦を慣れた様子で見守っていた。
「大体なぁ。陶冶は薄情なんだよ。俺があん時に助けてやらなかったら、下手すりゃ手前のGTOは今頃とっくに鉄屑なんだぞ?」
上からの物言いで反り返って言う環を前にして、陶冶はやや意気を挫かれる。
「ちッ……。何かある度に、すぐその話を持ち出しおる……。好い加減、その戦法は卑怯なんとちゃうか?」
卑怯と思いつつも屈してしまう自分への自嘲も含めながら、陶冶は苦笑いを浮かべた。普段は敢えてその話題を持ち出す事もないが、酒の席となれば確かに持って来いの話かもしれない。陶冶も自分の弱点だという事を分かってはいるが、その話をされる事が嫌なわけではない。
「まぁな……。俺かて、感謝しとらへんわけやないんやで? あれが俺らの『基点』なのは事実や。でもな。そういうんは、あんま無闇に持ち出すと、有り難味も薄れてまうで。」
相変わらず笑みを浮かべてはいるものの、やや陶冶らしさに欠ける穏やかなその笑みからは、陶冶の本心が窺える。
「しかし、始めお前と会うた時はビビッたがな。ゴツくて真っ黒なベンツのSUVから降りて来たんは、たるそうにした目付きの悪いガキやで? 因縁でも付けて来るんかと思うたで。」
「そのガキに救われたのは、何処のどいつだ? 大体、態度の悪さから言ったら手前に敵う奴なんて居るもんかよ。」
「あはは。私も最初に陶冶君を見た時は、正直背筋が凍ったね。車を停めた環を恨みそうになったもの。」
「あーあー。分ぁっとるわ! 俺は人相悪いっちゅう事くらいわな。」
半ば開き直って振り払うように手を振りながら、陶冶はグラスの焼酎を口にした。しかし、その酒の味は美味い。大して高いわけでもない、有り触れた銘柄の日本酒だが、酒の味というのは、その場の雰囲気にも大いに左右される。今、美味い酒を呑めている陶冶は、感情的にも間違いなく今を楽しんでいるのである。
「どうせ次はこう言うんやろ? メッキの牽引フックで惜し気もなくGTOを引っ張ってやったんだ、ってな。」
陶冶と初めて会った時に環が乗っていた、ベンツのSUV――AMG G55L。それは彼自身の所有物というわけではなく、並行輸入屋という彼の職業柄、転がしていたものだった。そしてその際、偶然乗り合わせていた千歳――。環の観点からすれば、親友の陶冶と恋人の千歳。彼にとって掛け替えのない二人との出会いが、その時だったのだ。だから、環が酔いが回れば決まってこの話題を持ち出すというのは、それだけその時が彼にとって貴重なものであったのだという事を指し示している。
「私もさ……あの時は飲み会の帰りに環が皆を送った後で、帰り道の方向の関係でたまたま私が最後に残ったんだけど、実は凄く緊張してたんだよ。それまでは環の事は良く知らなかったし、第一印象はもう本当に見たまんまだったから、ちゃんと家に送ってもらえるかどうかすら不安だったもんねぇ。」
千歳もこれまで同じ話を何度もして来た事を承知の上で、改めて出会いの時に想いを馳せる。
「あんだよ……。せめて千歳は俺の援護してくれたって良いんじゃねぇの? 誤爆も良い所だぜ……。」
「だーかーらー。第一印象『は』って言ってるじゃない。つまり、今は環の本当の性格をちゃんと分かってるよって事なんだから。」
「そういうこったな。お前は俺と違うて、見た目ほど悪い人間とはちゃうねん。お前も変に突っ掛かるから、いつまでも子供扱いされるんやで? 俺みたいに、もっと大人にならんとな。」
千歳と陶冶が揃って同意見な上に皮肉めいている事が余計に癪に障ったが、その真意を汲めないほど環も鈍感ではない。
「……ったく。手前らは……。」
それでもせめてもの苦言を呈した。
夜の帳に包まれて人気も殆どなくなった幕張新都心に、今宵も集う走り屋達。孝典も自らのRX−7に乗って、この場所へ来ていた。周回コース東の空き地で暫く時間を潰していると、やがてシルバーのS2000が空き地に入って来た。孝典はその車を見知っており、またS2000の方もそうであるようで、RX−7の隣に停まりそれからドライバーが降り立った。
「おっす。今夜も四天王は幕張に君臨されたりってか?」
何処か間違っていそうな古文調の妙な挨拶に、孝典は苦笑した。
「よせよ、江。その呼び名、面と向かって言われると結構恥ずかしいもんなんだぞ?」
幕張四天王と云う呼び名も、誰が言い出したかは定かではないが、通り名と云うのはそんなものであろう。今ではすっかり定着してしまっている。それは走り屋達の畏敬の念によるものなのだが、少なくとも孝典にとってはどうにも馴染めないものであった。
「良いじゃねぇかよ。俺も何か格好良い通り名で呼ばれてみたいもんだぜ。」
一方の江は、孝典とは対照的な印象を持っているようである。
「江だって充分速いじゃないか。お前の軽快なコーナリングは、俺なんかよりもずっと綺麗だぞ。」
「S2000の特性じゃ、コーナーで頑張るしかねぇだろ。NAだから、パワー面の不利は拭えねぇしな。」
江も幕張の中では速い方に属するのだが、孝典達ほど秀でてはいない。技術的な問題も去る事ながら、長い直線が多くスピードの乗るこのコースでは、江の言う通り車のパワーが勝負の分かれ目となる場合も多い。
とはいえ、だからといってNAのマシンを乗りこなしているのが江一人というわけではない。
「NAでだって速い奴は居るじゃないか。ほら……。」
今、NAのエキゾーストノートが幕張に響き渡っている事に逸早く気付いた孝典は、江にも耳を澄ましてみるように促す。やがて音の高鳴りと共に現れたのは、純白のボディを纏った沙和のNSX。その姿は近付いたかと思う暇もなく眼前を通り過ぎて行った。
「確かにあの車もNAか……。でも、NSXは別格だろ? 同じホンダ車で、同じように高見沢の工場で造られているとはいえ、S2000とは中身も位置付けも、そして値段もまるで比べ物にならないからなぁ。」
江がNSXの走り去った方を向きながら言うと、孝典もそれに言葉を続ける。
「しかも沙和のNSXはなかなか手が加えられてるっぽいし、そして極め付けはあの腕だ。そりゃ、速いわけさ。」
孝典がそう言うのを聞くと、江は僻み根性を滲ませながら言い返す。
「何だよ。さっきと言ってる事が違うじゃねぇか。結局お前だって、あのNSXが別格だって認めてんだろ?」
すると孝典は少々決まりの悪そうな顔をして笑った。
「まぁな……。けど、それはNSXだからってわけじゃない。俺達の中でも、沙和の腕はちょっと抜きん出てるんだ。どんな奴を相手にしても決して乱される事なく、確実に自分の走りをする。まるで相手の存在を意に介さないかの如くにな。冷徹に映る場合もあるが、あれだけの正確さはなかなか真似出来るもんじゃないぞ。」
それでも結局は沙和の事を持ち上げる孝典に対して、江は半ば自棄になって言った。
「けッ! どうせ俺は到底及ばねぇよ。……ったく、お前に言われたら余計に悔しくなって来たじゃねぇか。走るぞ。お前も付き合えよ!」
江の悔しがりに巻き添えを食らった孝典は、尚も決まり悪そうに苦笑いを浮かべながら、自らのRX−7に乗り込んだ。
見ず知らずの者達が何処からともなく集まって来るのが、走り屋の集う土地というものかしその一方で、走りに打ち込むという唯一の繋がりが不思議なまでの連帯感を生むのも事実であった。この当時の幕張は特にその傾向が強かった。
だから、誰が予想出来たであろうか。この時代の幕張の終末が、あのようなものになる事など――。